


2014.03.31
今年も4月と成り、桜の花が舞い上がる季節がやって来ました。最近の世の中の変化はとても激しく、かつ(マレーシア航空機事件のように)複雑怪奇な面が多く、正しい時代の流れを捉えにくい状態ではないかと感じます。そのような時は、春に成れば桜の花が咲くが如く、素直に「自然の摂理」に従った思考や生き方をして行けば良いのでしょう。そういう意味で、「四季」のある日本は恵まれています。何となく塞ぎ込んでいる日々を送っていたとしても、だんだんと気候が暖かく成って、美しい桜の花を目にすれば、気分は不思議と変わって行くものです。時間の流れとは本当に凄い。時の流れに身をゆだねる、水に流す・・・そのような自然界に在る「流れ」への意識さえ忘れなければ、自分自身の心を整え直すことは充分可能なのでしょう。そして今年も素晴らしい春がやって来ました。
現在の社会情勢や国際情勢、あるいは目の前の経済情勢や景気動向等、まさに先行き不透明な場所に立ち尽くしている私たちは、そのような厳しい外部環境と格闘しながらも、(その前に先ず)「自分自身」を生きて行くことに焦点を合わせるべきなのでしょう。私はいったい何のために生まれて、何のための生きているのか。少なくとも世の中と格闘する為では無いと思います。自分自身の成長の為、あるいは自分自身の幸せや生きる喜びを体感する為ではないでしょうか。外部環境とは、一人ひとりの「生きる喜び」を実現する為の時代設定(=背景)であり、舞台装置であり、物語設定だと思います。その物語が佳境(クライマックス)に入れば、自ずと「カタルシス」が起こり、自分自身の内側に感動や歓喜、生きる喜びが爆発するでしょう。この時代を生きている私たちは、相当ビッグなドラマを期待して生まれ出でたのではないでしょうか。時代が大きく進化進展する超激変期の中で、自分自身を生かしてみたい。まさに勇者の集まりです。
そのような激変期の中で、建設業の役割はますます重要に成るはずです。新しい時代造り、新しい国造り、新しい都市造り、新しい街造り、新しい住環境造り、新しい自分造り。それら全てを包み込む「生命場」を造ることこそが、建設業の使命です。建設業は、常に華やかな新ビジネスや花形産業の陰に隠れてしまいがちですが、人類が存在する限り永遠に存在し続ける「生命産業」の1つです。その建設業に今、人手不足の波が来ています。これは世の中の構造バランスを整える為の「平衡機能」の作動ではないでしょうか。世の中を陰で支えている「基礎」としての建設産業が手薄と成れば、社会全体の安定が維持できない。この不均衡の象徴として人手不足が現れたとすれば、この不均衡は必ず(早急に)是正されます。それは社会全体の根幹を揺るがす国家(人類)的な問題だからです。人間の生命に関わる職業、「生命産業」へのシフトが始まったシグナルです。
モノ造りの技術には、大きいも小さいも関係ありません。これからの「生命産業」としての建設業を支えるのは、お客様(住む人々)とより近い存在である「中小の建設会社」による「身近で親切なモノ造り」ではないかと感じます。激しい時代の変化に機敏に順応しながら、住む人の生命を(身近な存在として)守って行くことの出来る存在。そのような思いの強さこそが、この「生命産業」の核に成ると思います。
時代を超えて生き続けて行くものには、本質的な価値が在ると思います。短期的な(浮き沈みの)波ではなく、長期的な波に身をゆだねて、時間と共に生きて行くこと。昇る時は昇り、下がる時は下がる。けれども長期の波の方向はゆるやかに昇っている。自分自身をそのような「長期で昇って行く波」に置くこと。それが出来れば、短期の波に一喜一憂はしなくて済みます。世の中の動きに惑わされず、自分自身の長期の波に乗って行くこと。丸二の場合は建設業という悠久に続く波に乗りながら、お客様への思いやりを大事にして、自己の自立と成長を確立していく道を歩んで行きます。
※最近の写真

中野区大和町にて地鎮祭を行い、(その後)中野サンプラザにてお客様との昼食会を行いました。写真は(その時の)窓からの街並みです。

地元、武蔵野市吉祥寺本町で地鎮祭です。とても暖かい日でした。お客様のために、一生懸命に「良き建築」を造らせていただきます。

渋谷区神宮前にて地鎮祭です。素晴らしい青空の日でした。日頃から「良きご縁」をいただいている設計事務所様からのご紹介です。
2014.03.14
今日の夜中(AM2時頃)、愛媛で震度5強という地震がありました。大きな被害にならないよう心から祈ります。東日本大震災から3年が過ぎ、この一週間は「3.11への追悼」あるいは今後の地震予知(予測)等に関する番組が多く放映されていました。その中で、特に気に成っていたのが、東大の名誉教授の先生が、「この3月中に四国で大きな地震が起こるかもしれない」と話していたことです。全国に設置されている「電子基準点(地盤の上下動を測るもの)」の動きに大きな変動が起きているからとのことでした。もしこの予測方法と今回の地震との関連性を見出すことが出来れば、今後の地震予測への大きな一歩に成るのかもしれません。けれども地震そのものを(人間が)止めることは出来ないので、予測方法の追求と同時に日頃の防災意識が大切なのでしょう。さらには、地球(大地)への感謝の念を(一人ひとりが)持つこと。本当の根っ子はここに在ると思います。
前回のブログではロシアに関する話題を書きましたが、その後ウクライナ問題が表面化し、プーチン大統領の会見も報道され、現在はクリミア半島をロシアが制圧中とのことです。東欧の1つの国(地域)が、かつての冷戦構造を思わせるような緊迫した情勢と成り、私たちには解り得ない次元で、様々な戦いが始まったようです。このような戦いが起きると、必ずメディアは「こちらが善で、こちらが悪」という構図を設定します。その(作られた)設定(=シナリオ)に乗せられて、私たち一般人は短絡的な物の見方で世論を構成してしまいます。その繰り返しの中で、時代が築かれて行く。けれどもその結果として、世の中が良く成って来たかと言うと、良くなった面と、そうではない面の両方が混在していると思います。
実は「良くなったかどうか」という評価自体も曖昧で、それはそれぞれの国、勢力、地域、個人によって捉え方は違います。これだけ凄まじい技術の進歩があっても、未だに世界では貧富の差が大きく、根本的な問題が解決されたとは言えません。けれどもそのような中でも、日本はあの戦争以降、(おそらくある種の奇跡的偶然も重なって)比較的に幸福な道のりを歩んでいるように思います。地球レベルでの環境問題や人心荒廃の影響はありますが、それでも生きる意欲さえ在れば、生きる道が在ります。
今私たちにとって大切なことは、根本(本当のこと)への「追求心」だと思います。あの3.11で東北の大地と私たち日本人の魂は大きく振動しました。その後は、復興、再生が始まりました。けれどもそれは、形あるものを復元するという物理的な問題だけでは無く、もっと大きくて深い、真の「気づき」を見つける為だったのではないかと、最近感じる様になりました。このような時にこそ、私たちは物事の本質、あるいは本当の原因(真因)を追求し、発見し、そこを是正していかなければなりません。けれども、なかなか復興は進みません。福島の現状も厳しいままです。
3月8日にNHKで放映された「未来への手紙2014~あれから3年たちました~」を見ました。映画監督の是枝裕和氏をはじめ、複数のディレクターたちが被災地の子どもたちの3年を描いたドキュメンタリーです。震災から半年後に子ども達自身が撮ったビデオレターを振り返りながら、3年後の「今」の思いを本人たちが語ります。そこには大きな試練を乗り越えた(人間としての)精神的成長がありました。それにしても、子ども達にとっての「3年」とは、非常に長い時間軸ではなかったかと感じます。3年前の顔と今の顔とが全く違うからです。震災後の日々の日常(現実)を素直に受け止めながら、これからの自身の人生に向けて何か特別な意味を含めた熱い希望や期待を胸に秘めているかのように見えました。私はこの番組を見た時、未来の日本を造り上げて行くのは、きっと3.11を経験した子ども達ではないかと感じました。それくらい強く、頼もしく思えたのです。
他にも「東日本大震災から3年」をテーマにした様々な特集番組がありました。あの日、南三陸町の防災対策庁舎から(最後の最後まで)避難を呼びかけていた女性の死には、とても辛く悲しい思いが残りましたが、日曜日のNHKの番組の中では、その娘の死を乗り越えて懸命に生きようとする母親の姿が紹介されていました。涙なくして見られませんでした。そして今、ご両親は民宿を始めることにしたそうです。民宿の名前は「未希の家」。亡くなった娘さんのお名前です。防災意識と命の大切さを語り伝えて行くために・・・。震災から半年後、私が南三陸町に行った時、目にした防災対策庁舎の姿は、今でも心に焼き付いています。その記憶は決して忘れません。
話は変わって、先日謝罪会見を行った佐村河内守氏の事の顛末に付いてですが、一般論的な意味においては、やはり本当に愚かで、恥ずかしく、考えられない出来事だったと思います。ただ、一人のクラシック音楽ファンの気持ちとしては、一つの長大な交響曲がこの日本において誕生したことに、(確かにほんの一瞬の事ではありましたが・・・)心が躍ったのも事実です。佐村河内氏のプロデュース(構想プラン)、新垣氏の作曲という「ユニット」で発表して行けば、何も問題は無かった・・・。きっと2人は日本で誕生した新スタイルの「交響曲作家」として名を残したに違いありません。本当に残念なことです。
今の時代にクラシック音楽、とりわけ長大な交響曲などを作っても、「売れる」はずありません。それでも尚、生み出したい、売りたいという極度の欲求が「狂気」と化し、18年間に及ぶ「心の闇」を生み出したのでは無いでしょうか。幻となった「交響曲第一番」ですが、作者の名義を正しく修正することで、今後の演奏会の再開は出来ないものでしょうか。音楽そのものに罪はありません。この問題の真の論点は、この楽曲自体の評価に在ると思います。作者が誰であれ、どのような経過であれ、「良き音楽」には人は集まります。「音楽」が生んだ事件であれば、「音楽」の力で解決する。コンサートとCDが再開されれば、(逆に)相当な人気に成る状況です。そして多くの関係者が受けた心の傷や多大な損害も、もしかしたら(多少なりとも)解決できるかもしれません。そういう方向へ向かってもらいたいものです。
また、最近は「STAP細胞」の論文についても、いろいろな疑惑が出ている様です。上記の(佐村河内氏の)問題は、音楽の製作プロセスや製作者自身の人間性に「巨大な(故意の)嘘・偽り」が在ったのは確かですが、完成された「音楽(=作品)」そのものに嘘・偽りは無く、新垣氏作曲による立派な楽曲として世に生まれたのは事実です。STAP細胞についても同様にして、研究発表用データや資料の不備だけの問題なのか、あるいは「発見(=作品)」そのもの自体の誤りなのか、そこが大きなポイントだと思います。マスコミや報道は、こういう問題が起こると一斉に非難や誹謗中傷を始めますが、世のため人のために(善意の意識の上で)何かを生み出そうとする「志」への最大限の「敬意」と「感謝」を払った上で、事実を淡々と公開していただきたいと感じます。
マレーシア航空機の消滅、Jリーグの浦和レッズ戦における差別的な横断幕事件、大手電機メーカーの技術漏洩事件、そして昨日のような強風や愛媛の大きな地震。最近起きている様々な事件や出来事を見ていると、何かが堰を切って崩れ始めたかのような印象を受けます。今まで隠れて見えなかったものが出てくる時代。良きものも、そうでないものも一緒に・・・。全ては「3.11」から始まったのではないでしょうか。
3月11日の午後2時46分、心の中で黙祷を捧げました。日本だけでなく、世界においても、もう二度と大きな災害が起きませんように。世界中が平和で幸福でありますように。犠牲になられた方々の願いと祈りに応えられる自分たちに成れますように。その為にも、私たちはもっともっと時代の本質を追求して、物事の根本を理解して、そして認識し、さらには共認し、大本の部分から正していかなければなりません。東北の子ども達は、きっとその伝道者に成って行くと思います。「本当の生き方」や「本当の国造り」を追求する新しい日本の始まりです。
※最近の写真

恵比寿で地鎮祭です。お客様、誠にありがとうございます。これから誠心誠意の心で、「良き建築」を造り上げて参ります。

加子母森林組合(岐阜県)で、ヒノキの乾燥実験の報告会です。遂に、木材の芯まで含水率20%以下を達成しました。

加子母の隣町、下呂温泉(岐阜県)の早朝の空です。静かで、穏やかで、澄んだ空気がとても気持ち良かった。

三鷹の現場です。とても場内が整理整頓されていて嬉しかった。もうすぐ上棟です。「良き建築」の完成まで、がんばろう!

愛犬「じんべえ」君、井の頭公園で夕日を眺めています。何を考えているのかな。家に帰ってからのゴハンに決まってます。

井の頭公園の夕暮れです。モノクロで撮ってみました。なかなか良い雰囲気です。レトロ等もあったので、今度試してみよう。
2014.02.21
今朝のニュースで、ソチ・オリンピックの浅田真央選手のフリーの演技を見ました。涙が出ました。一日前のショートの演技を終えてから、きっと息すらも出来ない程の極限的な24時間を過ごされたことと思います。その深い、深い精神の闇の中から(自らの意志の力で)脱出することなど、通常の人間では不可能です。その闇を遂に自力で破り、平常心を取り戻し、その結果としてのフリーの演技は、何と自己ベスト更新だったそうです。しかも史上初の8回の3回転ジャンプを決めました。残念ながら(競技としての)メダルは逃してしまいましたが、「人間の強さ」としての(目には見えない)金メダルを授かったような気がします。それは、決して誰も(物理的に)手に入れられない種類のものでしょう。本当に見事でした。心から拍手と賛辞を贈りたいと思います。
浅田真央選手のフリー演技の音楽は、ラフマニノフの「ピアノ協奏曲第2番」でした。私が大好きな曲です。ショートの方はショパンの「ノクターン」でしたが、ショパンの音楽はどうも苦手です。「別れの曲」の印象が強く、どうしても寂しさや悲しさをイメージしてしまうからです。ラフマニノフはロシアの作曲家です。同じロシアで有名なのはチャイコフスキーですが、私はチャイコフスキーよりもラフマニノフです。なぜかと言うと、音楽的には分かりませんが、ラフマニノフの方が「深い」気がするからです。浅田真央選手が選んだ「ピアノ協奏曲第2番」がその代表曲ですが、「交響曲第2番」も素晴らしいです。特に第3楽章のアダージョは心が洗われる音楽です。私が学生時代に製作した8mm映画にも、このアダージョを使ったことがありました。
ロシアの作曲家と言えば、ストラヴィンスキーも好きです。「春の祭典」や「火の鳥」が有名ですが、「原始主義」と呼ばれる作風で、当時のクラシック音楽界においては超異端的な存在でした。それは音楽と言うよりも、原始的な激しいリズムによる音響絵巻の様なもので、所謂メロディーらしきものは(ほとんど)在りません。「春の祭典」の初演時は、遂に観客が(演奏中に)怒り出し、劇場内が大混乱に成りました。それでも私はこの「春の祭典」が大好きです。荒涼とした寒い寒いロシアの大地の奥深い「地底」から湧き上がる様な「超大なエネルギー」を感じるからです。浅田真央選手の精神にも、きっとこのような根源的なエネルギーが宿っていたのではないでしょうか。
ロシアの映画監督では、何と言ってもタルコフスキーです。このブログでも紹介した「惑星ソラリス」「ノスタルジア」「サクリファイス」の監督です。その映像の美しさには、本当に凄いものがあります。同時に、「音」に対する感性が独特です。水が流れる音、火が燃える音等、自然界に存在する「静寂なる自然音」を、まるで日本人が秋の虫の声に感じる様な「わび」「さび」の世界として表現しています。西洋の人なのに東洋の美意識が宿っているかのようです。最近DVDでタルコフスキーの初期の作品「僕の村は戦場だった」と「アンドレイ・ルブリョフ」の2本を観ました。共にモノクロの作品ですが、美しい映像と共に深い精神性を感じます。完全に商業主義に背を向けた作品ですが、このように完成後約50年が過ぎても未だに生き続けています。こういう「信念」の映画作家が、今は本当に少なく成りました。
また先日、妻と一緒に試写会に行き、もうすぐ公開のアニメーション映画「ジョバンニの島」を観ました。これは北方四島の1つである色丹島が、(終戦後)ソ連軍に占領された時の物語です。シベリアに連れて行かれた父親に会いに兄弟が雪の中を行くのですが、あらためて大切な家族を分断してしまう「戦争」の理不尽さを感じました。しかしながら本作では、ソ連軍あるいはロシア人を決して批判的には描いていません。そこにはロシア人の女の子との心の交流や、ソ連軍の寛大な措置も在り、現在の北方領土問題に対する問題提起と言うよりも、むしろロシアとの友好に力点が置かれているように感じます。
この物語の底流には宮澤賢治の「銀河鉄道の夜」が在ります。ジョバンニとは、「銀河鉄道の夜」の主人公の名前です。よって、世界全体の幸福を願った宮澤賢治の精神が、本作の真の主張ではなかったのではと感じます。日本とロシアの関係は、アメリカとの関係よりも薄く感じられますが、地理的にも近く、民族的な親近感もあり、また何か似たような「自然観」を共有している観もあり、これからもっと友好を深めて行ければと願います。ロシアのソチにて、遂に浅田真央選手の「心の地底」からの巨大エネルギーが爆発しましたが、あのフリー演技後の、悲しみと喜びと入り混じった何とも言えない表情は、これからの日本に何かを与えたのではないでしょうか。過去の艱難辛苦の全て含めて、喜びへ転化させること。日本もロシアも、きっとそれが出来ると思います。
※(本文と全く関係無いですが)我が家の「じんべえ」君です。雪が大好きで、雪の後の散歩に出る時に、「早く来い!」と吠えられてしまいました。この子はきっと雪のロシアでも生きて行けるでしょう。

2014.02.19
2週連続の全国的な大雪の影響により、関東地方に孤立した地域が生まれてしまい、未だ大変な状況が続いています。交通やライフラインが一刻も早く復旧し、普段の日常に戻れます様、心よりお祈りいたします。このようにして、地震にしても、台風にしても、大雪にしても、数十年に一度(あるいは数百年に一度)という大きな災害が頻繁に発生し始めていますが、あらためて自然界の力の猛威を感じます。今の地球環境の状況を考えると、今後もこのような自然災害はさらに増えて行くと想定されますので、可能な限りの防災意識と防災対策が必要でしょう。地震(=揺れに対して)だけでなく、竜巻、台風、大雪、大雨、洪水、津波、猛暑、寒波、噴火、火災、粉塵、大気汚染、ライフラインからの孤立等のあらゆる自然界からの猛攻に耐えうる(トータルとしての)強固な建物が必要です。建設業としての役割はますます大きく成ると思います。
けれども一方で、このような自然界が起こす現象の1つ1つは、私たち人間の生活にとって(実は)不可欠なものでもあります。現在開催中の「ソチ・オリンピック」にしても、多くの雪が降る地域だからこそ、開催都市に成れました。雪や寒さのおかげで、スキーやスケート等のウインタースポーツも発祥しています。結局私たち人間の方の都合で、降って欲しいとか、降らないで欲しいとか、ちょうど良い量にして欲しいとか、(恥ずかしながら)ついつい思ってしまう訳です。そのような(人間の)勝手な都合を自然界が常に聞いてくれる訳は無く、だんだんと「想定外」の事が増えて行くのでしょう。先日の二度目の大雪の日の夜は、ちょうど地元の友人たちとの会(誕生日会!)があり、みんなで大雪の吉祥寺の街を歩きました。それは、それは、とても楽しかった。多くの人は家に居て、開いているお店もほとんど無い中、大雪をたくさん浴びながら、人通りの少ない街中を歩くなんて、確か小学生の頃以来です。自然界に対する畏れと共に、感謝と喜びを感じることも大切だと感じました。同時に謙虚に向き合って、防災準備をしておくことも。これから自然界との付き合い方が、私たち人間にとって重大な課題に成っていくと思います。
さて、その「ソチ・オリンピック」ですが、羽生選手とレジェンド葛西選手の大活躍には胸が躍りました。本当に良かったです(心からおめでとうございます!)。努力の成果はいつかきっと報われる。自分を信じて、決して諦めずに、前へ向かって前進するのみ。多くの人は(きっとどこかで)諦めてしまうのでしょう。羽生選手は、あの東日本大震災でスケートリンクを失いました。レジェンド葛西選手は、幾度ものオリンピックに出場しながらも、不運の連続でした。それでも二人は決して諦めず、可能性を信じて前へ進み、遂に栄光を手にしたのです。レジェンド葛西選手は、他国の選手からも尊敬され、チームの為に涙を流しました。そして私はこれを見た時、日本の行くべき姿を想起したのです。他国から尊敬される国。みんなの期待に応えようと涙を流す国。積年の艱難辛苦を乗り越えながら、愚直にただ1つの道を歩み続ける国。そこに「レジェンド日本」の姿が見えました。
世界で日本ほど尊敬されている国柄は無いそうです。その「国柄」自体が大変な価値ではないかと思います。南北、東西に長い地形で、美しい四季(自然)があり、3.11の時に「東北」が見せた素晴らしい人間性の宿る国。(他国に比べて)国からの支援が少ない中、自身の純粋な思い(夢)だけでオリンピックを目指す人たちがいる国。ああ、日本の良さをもっと世界に知ってもらいたい。自然信仰が残り、自然を大切にし、自然界と共に生きようとする日本を知ってもらいたい。東日本大震災から始まった自然界からの大試練を乗り越えて、真の世界の雛形に成り、他国を正しい道へ導く役割を果たす。日本は、それが出来る国だと思います。レジェンド葛西選手の涙を見て、それが揺るがない確信と成りました。
※武蔵野市吉祥寺南町(井の頭通り)の現場です。おかげさまで無事完成し、引渡しが終わりました。お客様に心から感謝いたします。

※池袋の立教大学の前の現場です(右が現場、左が立教大学です)。もうすぐ躯体工事が完了します。お客様に心から感謝いたします。

2014.02.08

予報通り、東京は雪に成りました。仕事柄、現場の事を考えると、冬の降雪は少ない方がありがたいのですが、子どもの頃を思い出すと、雪が降った時のワクワクした気持ちが蘇ります。そう言えば、夏の夕立や雷が鳴った時も、怖さと同時に、何かドキドキ感、ウキウキ感がありました。きっといつもの日常とは違う未知の体験に胸が躍ったのでしょう。昔は自然の変化にもっと敏感で、もっと素直に受け入れていたように思います。けれども今は、人間側の都合の方が優先と成ってしまい、自然をコントロールしようとさえしています。本当は人間の方が自然界に含まれている側なのに・・・。
そしてソチオリンピックが開会しました。冬のオリンピックとしては、長野オリンピック以来、日本人の活躍が大いに期待できそうです。ただいつも思うのは、相手を負かして喜びを得るというスポーツの持つ根源的な疑念を、私たちは一体どのように認識して行けばよいのかと言う点です。そもそもそのような疑念を持つ人自体、あまりいないと思いますが、世界の平和を願うオリンピックの祭典を目にするたびに、いつもそのように感じるのです。日本を代表して出場する選手の方々が、世界の選手たちと仲良く成って欲しい。オリンピックが開催される度に、世界中のアスリート達の輪が広がって、国境を越えた和になって欲しい。それが本当に期待するところです。
自然界はそれぞれの存在が、勝ち負けで争っている訳では無く、お互いが固有の価値を有し合いながら、全体が調和しています。小さな虫も、大きな山も、美しい花も、枯れた草も、それぞれが素晴らしい価値と役割を持っているのでしょう。この見事なまでに完成された雛形を、もし人間社会に転化できたならば、本当に素晴らしい世界が生まれるのではないかと想像します。けれども、そうは成らないのも世の中の現実。このような矛盾やジレンマの葛藤の中で、(それでも)少しでもより良く成って行こうとするプロセス(体験・経験)が人生の本質なのでしょう。
今、佐村河内守さんのゴーストライター問題が、世間で大きな話題に成っています。私もNHKの特集を見て、深く感動し、CDを一枚買いました。しかしながら、そのあまりにも重く、暗い音楽の様相を感じて、未だCDの封を切らないままでいました。そして今回の報道があり、驚きと共に、一人の人間の持つ絶望的な苦悩を感じました。もちろん、自身が作曲していないにも関わらず、そのように装ったことは大いなる罪でしょう。しかしながら、佐村河内さんの脳内に在る曲想イメージを指示されない限り、真の作者である方が、そのような巨大な音楽を創造することは(きっと)出来なかったに違いありません。佐村河内さんは立派なプロデューサーとして、真の作曲者と共に、良き音楽を発表して行けば良かった。譜面が書けなくても、ベートーヴェンのような悲劇性を身に纏わなくても、プロデューサーとして価値は微動だにしなかったはずなのに・・・。
この問題が発覚後、佐村河内さんは全てを真実として認めています。普通であれば、お互いによる訴訟合戦に成るところです。真の作曲者の方も、佐村河内さんの罪がこれ以上、塗り重ねられないようにと、真の愛情と勇気ある行動をされたと思います。ここで終って、本当に良かった。ここにまだ、何か一縷の救いが残っています。佐村河内さんのCDは発売中止と成りましたが、逆に注文が殺到しているそうです。確かに、社会性という意味においては間違いなく「偽物」ですが、偽物を身に纏った一人の人間の絶望が音化された芸術としては「本物」なのかもしれません。幸い、私の手元には(もう二度と手に入らない)一枚のCDが在りますので、いずれ封を切って、偽者が想起した本物、真の作者が創造した本物を聴いてみたいと思います。お互いに極度の罪の意識を抱えながら、それでも尚、良き音楽を創造しようと命を削った二人の合作音楽を・・・。
「自然に生きる」ことが大切なのでしょう。毎日、呼吸できる幸せに感謝して生きること。そのこと自体が素晴らしい奇跡的なことなのに、私たちはそれを当たり前の事と思い、常に間違った選択をしてしまいます。佐村河内さんの件は、決して他人事ではありません。みんな(大なり小なり)偽りを身に纏って生きていると思います。そのような覆いをいち早く撤去できたならば、自然に生きる道が見えてくるのでしょう。大自然から学ぶこと、まだまだたくさんあります。
2014.01.25
街を歩いていて、ある政党のポスターに「安定」という文字を見つけました。私たち人間は、不安、不安定、先が見えない、先が読めないことを極度に恐れて生きていると思います。だから誰しもが「安定」を求めます。経済情勢が不安定に成れば、就職先もさらに安定志向が強まるでしょう。それは人間の根源的な心理として、当然理解できます。ただ、そもそも「安定」とは何か、「安定」とはどう言う状態なのかが曖昧です。多くの人々にとっての「安定」とは、「もうこの先、特別何か(苦労)をしなくても大丈夫」な状態ではないでしょうか。ここに就職したらもう安全。これだけのお金があればもう(何もしなくても)大丈夫。多分きっとこのような感覚だと思います。つまり「安定=静止」という捉え方です。
そのように考えた時、同時に何か・・・「本当にそうかな」と言う違和感も残ります。例えば、私たちが住んでいるこの地球は、宇宙空間に「安定」した状態で浮かんでいます。そのことに対して、私たちは(当然)全く不安感を覚えていません。そもそも、そのこと自体を忘れて日々を生きています。けれども、その完璧なまでの「安定性」は、実は時速1400 kmの自転運動によって保たれています。これだけの超音速、かつ全く狂いの無い(必死とも言える)「動き」の連続によって、地球は宇宙空間で静止(=安定)しているように見えているだけです。とすれば、安定は静止状態と言うよりも、必死の運動状態の連続によって維持されているのではないかと考えられます。
「もう安心、止まって大丈夫」と思った瞬間に、自分自身の「自転運動」が止まり、本当の意味での不安定が始まります。世の中の状態がどうであれ、自身の環境や境遇がどうであれ、自分自身が何かに向かって「自転」さえし続けていれば、そこには真の「安定」が発生するのではないでしょうか。昨日のTV番組では、東大を出て環境省に努めながら、赴任先のルワンダで廃棄物対策を行った後、そこで自ら環境省を退職し、ルワンダに残った一人の人物を紹介していました。彼は、エリート官僚という職と勲章を捨て、個人で途上国に貢献する道を選んだのです。人はそれを「安定を捨てて、もったいない」と言うでしょう。けれどもこの人にとっての安定とは、そこで自身を「自転」させ続けることだったのではないでしょうか。
常に何かに挑戦し続ける「運動性」こそが、本当の「安定」だと思います。「もう安心だ」と、静止してしまった瞬間から、恐怖の「不安定」がやってくる。そのように理解することがもし出来たならば、日々何かをしなければ成らない状態で、毎日を必死で動き続けていることは、むしろ「ありがたい(幸福な)状態」なのかもしれません。お金に対する考え方も一緒で、多くの蓄えがあること自体が(決して)安定ではなく、そのお金が順調に(清浄に)「回っている(動いている)」状態こそが、本当の安定と言えます。しばしば、大きなお金を持ちながら、決して幸福な人生で終らなかった人がいます。きっと、お金を良い形で社会へ回さなかったことが原因ではないかと想像します。つまり、大きなお金を得た人ほど、大きな責任(=役割)を負う訳です。
この度、楽天イーグルスの田中将大投手が米ヤンキースに入団することが決まり、巨額の契約金額が新聞紙上を駆け巡りました。これは、田中投手にとって、むしろ大きな負担(責任)に成るものでしょう。「それだけの成績を残さなければ成らない」という意味では無く、このお金をどのように世の中へ回していくかという面においてです。ただ田中投手は、楽天時代から様々な形で(決して目立たないように)多くの寄付をして来たと聞きます。多分、そのような人間性であったからこそ、昨年の様な偉大な成績と今回のメジャー行きを引き寄せたのでしょう。ならば今回の報酬についても、さらに生きた使い方をされて、またさらに大きな役割を与えられるに違いありません。本当に物凄い人物だと思います。
富や幸福、知識や知恵を、自分自身だけで止めないで、広く社会(他者)へ流していく。流して行けば、その時は(一瞬)減ってしまうように見えますが、(けれどもいつか)必ず与えた分がさらに大きく成って、別の方向から入って来る。そしてそれをまた流していく。この連続する運動が真の安定であり、その最初の一手は(間違いなく)「与える(捨てる。損する)」から始まるということです。「入ってから、出す」のではなく、「出してから、入る」の順です。だから難しいし、厳しいし、怖い。勇気が無いとできない。挑戦心が無いとできない。この不安に打ち勝てる者こそが、最後に真の安定を得られるのでしょう。
「安定」とは「得る」ものではなく、「在る」ものだと思います。必死で動き続けること。世の中の為に何かをやり続けること。その「状態」を言うのだと思います。だから、誰かの為に、社会の為に、今を必死で生きている人は、みんな(既に)「安定」を手にしている幸福な人だと思います。

※吉祥寺南町の井の頭通り沿いの現場がもうすぐ完成です。お客様と自然の恵みに、心から感謝いたします。ありがとうございます。
2014.01.20
2014年が始まり半月が過ぎましたが、工場の事故、海上の事故、行方不明事件等、類似する出来事が数多く発生している様な気がします。昨年末には冷凍食品の事故がありましたが、今度は浜松の学校給食で大規模なノロウィルスの被害が起きました。今後はこのようなウィルス対策も重要に成って来るのでしょう。同時に「食」に対する注意喚起も必要なのかもしれません。また17日は、1995年に発生した阪神淡路大震災から丸19年でした。あの時、テレビの画面で見たビルや高速道路の倒壊現場、地震後の大規模火災の様子は、未だに脳裏に焼き付いています。それから16年後の3月11日には、その恐怖が再びやって来ました。このリピートし続ける現象を止めなければならない。けれども、なかなか止まらない。きっと何かが足らない。
今回の東京都知事選挙では、「脱原発」が1つの争点に成りつつあります。日本で最大の電力を消費する都市として、極めて大きな課題の1つだと思います。エネルギー問題の根本解決は、戦争、経済、地球環境に多大な(良き)影響を与えるはずです。私たちが原発問題を考える時、常に未来の全世界(=地球)の安全と平和と発展を「思い」ます。実は、その意識こそが最も大切なことではないでしょうか。景気回復(発展)を優先する人も、安全性を優先する人も、共に「未来のため」という視点を置きます。その上で、様々な方法論を展開して行くのです。けれども方法論はあくまで戦術ですので、状況に合わせて変化するものです。目的が一緒であれば、その実現方法が違っていても、どこかで共有できる場所(着地点)が見つかるはずです。このようにして原発問題に真剣に向き合うことが、国や世界の未来を「思う」ことに繋がり、その結果、(今はまだ見えない)最良の答えを導き出せると期待します。
あらゆる問題や課題を解決する(=終わらせる)根本は、その問題や課題へ向き合う思考力や追求力の強さではないかと感じます。最終的に、その改善方法(戦術)は目に見える形と成りますが、その大元の種は、まさに人間の「思考力」や「追求力」という意志の力のはずです。経済も原発も戦争も、本当に「良き未来」を思考して、追求して行けば、必ず良き方法が見えてくると思います。今はまだ、その「思考力」と「追求力」が弱いだけではないでしょうか。これは政治家だけの事を言っているのではなく、私たち国民全員の意志の力が弱いのだと思います。目先の方法論を戦わせる前に、どのような「良き未来」を創造するか・・・その「思考力」と「追求力」をみんなが持つこと。経営も同様です。社員全員が、本当に「良き会社」を思考して、追求して行けば、必ず良き結果は出て来ます。
世の中で起きている事。自分の人生で起きている事。みんな、自分自身の思考力と追求力を鍛える為の練習(レッスン)です。このレッスン・プランは一人ひとりメニューが違うので、誰かに代わってもらう訳には行きません。自分自身でオリジナル・メニューをこなして行くしかありません。でも、1つ1つをクリアーしていくことで、自分自身の思考力と追求力が高まります。これは最高に喜ばしい経験です。しかも練習メニューである以上、必ずクリアーできる答えが用意されているはずです。だから安心して、自身の問題や課題に真剣に向き合って、全力で思考し、全力で追求して行くこと。問題や課題が大きいと言うことは、自分自身の器が大きいということ。世の中が大転換しようとしている今、全ての存在が大きく飛躍できるビッグチャンスが来ています。自分自身の「思考力」と「追求力」を鍛えて、この時代を生きる価値を掴もうと思います。
2014.01.01
新年明けましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
平成26年元旦
年末年始、東京はとても良い天気です。今朝も毎月1日と同様、早朝に(スーツとネクタイ着用で)地元の氏神様(武蔵野八幡宮)へお参りに行き、感謝の思いをお伝えして参りました。元旦のお参りは早朝に限ります。人込みも少なく、とても清々しい空気でした。参拝後、そのまま会社へ行って、神棚の水を替え、御挨拶。その後、初日の出に向かって手を合わせて御挨拶。もちろん家を出る前には仏壇(御先祖様)へ御挨拶。「一年の計は元旦に在り」と言いますので、今年もこのような「礼」から始めました。そして今は、会社に年賀状が届くのを待ちながら、こうしてブログを書いているところです。
年が明けて、あらためて昨年一年を振り返ると、もう遠い昔のことの様に感じます。全ては過ぎ去っていくもの。良い事も悪い事も。結果、最後に残るのは経験と思いだけです。映画「かぐや姫の物語」の主題歌である「いのちの記憶(作詞作曲:二階堂和美」の歌詞に、こうあります。「いまのすべては過去のすべて」「いまのすべては未来の希望」と。「いま」とは、自分自身が生きた全ての過去の「結果」です。同時に、この先の未来を決定する「原因」です。と言うことは、過去を後悔したり、未来を不安に思うことは、全く無意味なこと。「今を懸命に生きること」こそが、未来を生きる自分自身への最高のプレゼント(結果)に成るのだから。「いま」という時空の中で、自分自身をただ輝かせること。自分自身を生き切ること。生きている手応えを感じること。そのような気づきが大切なのだと理解しました。
日本は本当に恵まれている国です。しかしながらその状況に胡坐をかいてしまい、おかしな方向へ行ってはいけません。決して、恵まれていることへの感謝を忘れてはいけません。結局のところ、全ての根本はこの「感謝」に在ると思います。感謝が不足すると、必ず人も会社も国もおかしく成ります。丸二はかつて「ありがとう」という言葉(言霊)を企業メッセージとして使用していました。けれども、その「ありがとう」とは、あくまで人間同士の「挨拶」や「御礼」としての表現の域であり、もっと大きく、もっと深く、もっと根元的な「感謝」には遠く及ばないレベルだったのです。そのことに気が付いた時、とても恥ずかしい思いでいっぱいに成りました。すぐに企業メッセージを取り下げて、深く深く考え続けました。もっと本質的な「感謝」を認識しなければ成らないと・・・。
そして、気づいたのです。私たちは建設会社です。ありとあらゆる種類の建材を使って、建物を造っています。これらの建材は(よく考えると)全て自然界から生まれています。もちろん人工的な加工製品も在ります。けれども、それらも元は自然界にある物質を組み合わせて出来たものです。と言うことは、私たちは、この大自然に存在している物質を、(自然界に対して)無断で、無料で、使わせていただき、企業経営をさせていただいていたのです。ああ、何て勝手で失礼なことをしていたのだろうか・・・。その全ての根本に対する「感謝」が、先ずは大切ではないか。建材を使っているのではなく、使わせていただいている。建物を造っているのではなく、造らせていただいている。水や空気がもし無くなったら、人間は数十秒で死んでしまいます。生きているのではなく、生かされている。「ここ」への感謝。そう思い至った時、私たちは、「自然の恩恵に感謝できる会社造り」を目指すことにしました。この原点が無ければ、本当の意味での(人々への)「ありがとうございます」という思いは生まれない。その事に気が付いたのです。
このようにして私たちは「感謝道」を歩み始めました。真の「感謝」、お客様への真の(誠心誠意の)「ありがとうございます」を実践し続けることで、良き経験と良き思いが育まれるはずです。それはきっと必ず、「未来の希望」を造り上げて行くでしょう。今年も「感謝」で駆け抜けて参りますので、何卒よろしくお願いいたします。尚、今年の「ニコニコ通信:新年号」の挨拶文を下記に転載しましたので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
【ニコニコ通信:新年号~社長コラム】
新年明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
昨年10月8日に創立60周年を迎え、また新たな年明けと成りました。これもひとえに、全てのお客様並びに関係各位の皆様のおかげと、厚く御礼申し上げます。誠にありがとうございます。昭和28年の創立当時とは全く異次元のような60年後と成りましたが、それでも建設業の原点は変わらず、人々の生活と生命を守り、人々の喜びと幸せを育む場を造ることに在ります。時代の流れによって、その役割や存在感は確かに変化はしていますが、私たち丸二は、「自然の恩恵に感謝する」という根源的な理念の下で、「良き建築」と「良き住環境」を懸命に社会へ提供し続けて行く決意です。この60年で最も大きな変化と言えば、地球環境の問題があります。毎年のように過去に例のない異常気象が起こり、人々の生活に多大な影響を及ぼしています。そのような自然界の異変の真因こそ、私たち人類の生き方に在ったのは間違いの無い事実ですが、それでも私たちは、毎日を安心して、安全かつ快適に暮らして行かなければ成りません。日々の防災意識を持ちながら、この時代を乗り越えて行ける本物の建築を、私たちは造り続けて参ります。昨年秋に行われた伊勢神宮の式年遷宮が無事に終わり、これからの20年は、今までの「米座(平和の時代)」から「金座(激動の時代)」へ移行すると言われています。いずれにしても、あらゆる物事が大きく動き出す時代に入ろうとしていますので、先ずは自らの精神を確立(自立)して、その激動のエネルギーを良き方向へ導いて行きたいと思います。最終的には、会社で言えば「経営理念」、個人で言えば「人格形成」が、「見られて行く」時代に成るのでしょう。そのような意味において、これからの20年は「反転する時代」です。良いものを誠実にご提供する良心的な経営が、「力」を得て行く時代に成るのでしょう。丸二は、そのような良き時代へ向けて、1mmの前進を続けて来ました。世の中が(あらためて)建設業を再評価し、新しい建築を求める時代に成った今こそ、私たちはその期待に応え、その期待を超えて行くことが出来るのです。よって、この2014年の年明けは、丸二の「次の60年」への新たな大きな門出と成ります。私たちが更に一層、皆様のお役に立ち、皆様の喜びと幸せを創造すべく、今後も最善を尽くして参りますので、本年も何卒ご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。ありがとう御座位ます。
2013.12.27
明日12月28日は会社の仕事納めです。今年も本当に素晴らしい一年でした。もちろん全てが良い事ばかりでは在りません。けれども、人も会社も様々な経験を通して成長して行くものです。ここ数年来の激動の時代において、こうして1つ1つの年を越して行けることへの感謝の思いでいっぱいです。どのような出来事も、自分自身に対するタイムリーな課題であり、ご褒美です。そう考えると、この世の中の仕組みは想像を絶する凄さだと分かります。一人ひとりの人間の全てが、個人の成長の為の出来事と出会いながら、その相手の人も、あるいはその総和の社会全体も、同時に必要な経験と向き合っているからです。どんな天才科学者でも追いつけない程の計算式の下で、全ては関連付けられ、管理運営されているのでしょう。そう成ると、今現在の世の中の変化も、きっと大きな意味合いを持っているのではないでしょうか。今を生きる個人個人が、自身の課題を解決する為に、「今」という時代が必要だったのかもしれません。世の中全体と自分自身の人生は決して無関係でなく、極めて太い線で結ばれていると思います。
今年もおかげさまで仕事量が多く、とても充実した一年でした。また中期経営計画も立て、会社の未来像へのイメージ化も出来ました。お客様に「良き建築」をお届けすることで、これからの激動(あるいは防災)の時代の中、私たちの役割は確かに拡大するでしょう。否むしろ、かつて無いほどの影響力が生まれるかもしれません。これまでの建設業は、ずっと下降線を辿って来ましたが、人々の生命と生活を守る基幹産業、もっと言えば「生命産業」としての復活を果たし、いよいよ社会に貢献しなければ成りません。震災の復興、国土強靭化、老朽化したインフラの整備、オリンピック対策、耐震・防火への対応、地域環境の清浄化、住まいの再建築、住まいの修繕、強固な建物、長寿命化・・・。人間が生きて行く上で、絶対的に必要不可欠な「衣(医)食住」の一角として、精神的にも肉体的にも負荷の多くなる時代の中、安らぎと寛ぎと安心安全をご提供する仕事。それが建設業です。
今、業界では職人不足が問題に成っています。この傾向はますます拡大するでしょう。同時に技術者の高齢化も進んでいます。この流れは、あらためて(「虚業」に対する意味での)「実業」への回帰を積極的に促す為の(あえて)演出された状況設定なのかもしれません。今後、最も人手を必要とする(であろう)建設業界に、人手不足、若者不足という課題がある。これは裏を返せば、その「反転」に対する期待では無いでしょうか。リアリティー(実体)のある仕事への回帰。そこまで読み取ることが出来れば、今後の職人不足や若者不足は一気に流れが変わってくると感じます。建設業の素晴らしいところは、経験者、熟練者には敵わないという面があることです。若い人の方が良い仕事が出来る業界はたくさんありますが、建設業はそうは行きません。やはり、実際の仕事をして来た人の経験には敵わないのです。そういう意味で、今現在の若者不足の中でも、この業界はしっかり成り立っています。
けれども、そろそろ熟練者の技術や経験を引継ぐ世代も必要です。そのようなタイミングの中で、今の建設需要の増加が起きました。これは天の計らいでしょうか。何か全てが計算され尽くしている。そのような印象を持つのです。熟練者や高齢者が優位と成る仕事は本物だと思います。結局のところ、最後の最後まで社会に貢献できる役割は尊いものだからです。年齢に関係なく、いつまでも出来る仕事こそが、その人の使命であり、役割ではないでしょうか。会社には定年がありますが、仕事には定年はありません。建築は、死ぬまでやり続けられる仕事の1つだと思います。伊勢神宮の御遷宮は20年に一度ですが、そのお蔭で、日本古来の建築技術が脈々と受け継がれています。建設業も(同様に)約20年振りに需要の喚起が発生しています。これも決して無関係では無いと思います。
来年は一体どのような年に成るのでしょうか。今年以上に激動の年に成るのは間違いないように思います。いずれにしても物価の上昇は今後もますます続いて行くでしょうから、そういう意味で、消費行動が早まり、景気を支えて行く可能性はあると思います。ただその一方で、社会全体の仕組みや個人の生き方を変えて行こうとする流れも加速するのでは無いでしょうか。その根底にあるものこそ、自分自身の中に在る良心との対話です。今までの社会全体に存在していた強制的(物質的)な価値観から抜け出し、自分自身の良心の声に従って生き始める人が増えて来るような気がします。先日、とても尊敬するある方からこう言われました。「今までは良心的な会社(人)が苦しかったが、これからは良心的な会社(人)が良く成る」と。これは逆に言うと、良心を裏切る経営や生き方をしたらダメに成るという、裏返しの意味にも聞こえます。全ての人間の生き方が「見られている」時代の中で、いよいよ個人の内面性に対する評価が顕在化する時代が始まろうとしています。それはむしろ厳しい時代ではないかと思います。けれども極めて爽快で清々しい時代でもあります。来年も一年、自分自身の良心と共に、楽しく経営と人生に向き合って行こうと思います。ありがとうございます。
※挑戦し続ける監督たち

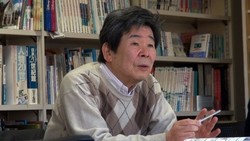
建設業と同様に、映画の世界でも70歳を超える熟練監督が未だに注目を集めています。どんな若手監督よりも衝撃的かつ挑戦的な作品を創り続けているからです。本ブログで何度も紹介している大林宣彦監督やジブリの高畑勲監督はその良い例です。先日、このお二人の製作現場を追うTV番組が相次いで放映されました。大林宣彦監督の方は、NHKの特集で、前作「この空の花~長岡花火物語」に引き続き、今度は北海道の芦別を舞台にした「野のなななのか」という古里映画の紹介です。今回も北海道の豊かな自然の中で、戦争や生と死を題材にしています。またきっと驚くべき作品に仕上がっていることでしょう。公開は来年で、今から楽しみです。
一方、高畑勲監督の方は、WOWWOWの番組で、前編と後編の2回に分けて放映されました。もちろん内容は、現在公開中の「かぐや姫の物語」です。この映画の評価は(驚くほど)真っ二つに分かれていて、賛否両論状態がさらに激化しています。未見の方は、年末年始にぜひ見てください。きっと「1点。ただの竹取物語。長い。つまらない」か、「満点。歴史的大傑作。不覚にもかぐや姫で泣いてしまった。また見る」のどちらかでしょう。番組を見て初めて知ったのは、高畑監督は「絵を描かない」ということです。アニメ映画の作者が絵を一切描かないなどとは、思っても見ませんでした。高畑監督は自分自身のイメージや考えを「言葉」で表現するのみ。あるいは手振り身振り。その下で、トップクラスのクリエーター達が、その指示に従って、懸命に作業を進めるのです。同じジブリの宮崎駿監督とは全く違います。まだ勢いの残っている手書きの筆の線をそのまま動画にするという、通常のアニメ制作のシステムでは考えられないやり方は、ジブリの製作現場を崩壊させたそうです。よって今回の「かぐや姫の物語」は、新たに別のスタジオを作って製作に入りました。それでも作業は難航を極め、公開は延びたのです。それにしても、一体このエネルギーはどこからやって来るのでしょうか。売れる映画を作るという発想は微塵も無く、自身の魂から発せられる「言葉」の実現だけに生きる。この「目には見えない」力と波動の合った人のみが、「心が震える感動」を味わえるのかも知れません。リーダーにとって「言葉」は生命です。あらためてその事に気づきました。私はお正月に、また家族と見に行く予定です。多分きっと、この映画は100年後も名作として存在していると思います。
2013.12.06
喪中のお葉書で、恩師が亡くなられたことを知りました。私の小学校時代の先生で、私自身の幼少期における精神的支柱とも言える存在でした。先生から教わったこと、山ほどあります。そのほとんど全てが、今現在の自分自身の根底に息づいていると思います。私のような、おとなしくて、目立たなくて、成績も(可もなく不可もなく)ごくごく普通の子どもに対しても、多くのことを真剣に、時に厳しく、時に優しく教えてくださいました。あの時、先生がおっしゃっていたことは、今思うと、子どもに話すようなレベルの内容では無かったように思います。所謂、先生が生徒に対して「ああしなさい、こうしなさい」という種類のものでは無く、もっと広くて大きくて深いものでした。
先生の専門は歴史(日本史)でしたが、その歴史の授業においても、単なる年表的な説明ではなく、例えば合戦の風景や情景がありありと思い浮かべられるような、まさに「物語絵巻」を見ているかのような臨場感があったのです。またクラスの中で何か問題が起こると、授業を止めて、その事柄について真剣に叱り、同時に包み込むような優しさで(何時間も)語りかけてくれました。先生のお宅にも何度も友達と遊びに行きました。このクラスには、多くの教育関係の方々が授業見学に来られていましたが、学業と心の教育の両立が成されていたと云う意味において、(今から思うと)随分時代の先を行っていたように思います。そして多くの同級生たちは(その後)優秀な進路へと進んで行きました。
先生との思い出の1つに、移動教室で日光へ行った時のことが在ります。泊まった宿泊施設の部屋がとても広く、2段ベッドが(確か)10台くらい有って、ひと部屋20名くらいでワイワイと騒いでいました。そこへ先生が入ってきて「静かにしなさい」と注意されたのですが、その際、あまりにも部屋が散らかっており、それぞれのベッドの上もグチャグチャ状態で、先生から「何だ、この汚い部屋は!」とさらに厳しい雷を落とされました。ところが、その中で1つだけキチンとしたベッドがあり、先生から「そこは誰だ」と聞かれたのです。それは私のベッドでした。自分はただグチャグチャ状態が嫌いなだけで、好きでキチンとしていただけでしたが、「僕です」と答えると、「トモキか。偉い」と言われました。ただ、それだけのことでしたが、自分の心の中に、何か小さな灯りが燈ったような気がしました。先生はそう言って部屋を出て行きました。みんなは静かに身の回りを整理し始めました。
身の回りをキレイにしなさい。両親に感謝しなさい。先生に教わった2年間の中で、今でも心に刻まれている大切なことです。私という、弱くて小さな生命の一番奥底に記憶された2つの規律は、その後の人格形成の種と成りました。その後も、素晴らしい恩師との出会いがあり、事に応じて、「身の回りをキレイにしなさい」「清浄感を持ちなさい」「掃除をしなさい」「靴を揃えなさい」「ゴミや不要なものはすぐ捨てなさい」「自然の恵みに感謝しなさい」「太陽に感謝しなさい」「食べ物に感謝しなさい」「挨拶をしなさい」「時間を守りなさい」「約束を守りなさい」と、教わり続けました。それら全てが、あの頃「先生」からいただいた「種」に与える「水(養分)」に成っていたのではないか。ああ、そうだったのか・・・。
清き水は淀みなく流れ続けます。身の回りを清浄感で保つということは、まさに自分自身の人生に淀み(停滞)を作らないためです。ゴミはもちろん、使わない物も、すぐに捨ててあげること。それによって、その物(物質)はいったん壊され分解されますが、すぐに新たな物体として再生され、別の人々の生活のお役に立ち、また新たな生命(価値)を生き始めます。使わない物を使わないまま放置しておくことは、物に宿る生命を殺していることなのです。だからこそ、使わないものは(できるだけ)持たないようにする。使うものは、長く大切に使い続ける。それが本当の「もったいない」の心。地球環境が大変に成って来たのは、このような意識を人類に気付かせるためだったのではないか。3.11が起きても、なかなか直らない心の習慣。そのような時代を生きて行く上で、「先生」の教育は、未来の子ども達を救って来たのではないかと、ふと思います。
先週の土曜日、とても尊敬するある方の新築祝いのために、静岡県の可睡という地に(その方の親友の方々と一緒に)日帰りで行ってきました。新しい住まいはとても美しく、超シンプルで、(隅から隅まで)清浄感で満ち溢れていました。いかに「持たないか」を追求すると、このような良き姿・形に成るのでしょう。このような良き生活・人生に成るのでしょう。家そのものが、住む人の生き方を証明していました。良き建築は良き人生の写し鏡。であるならば、自身の家の状態、部屋の状態は、自分自身の心の写し鏡と成ります。そのように気づいた時、身の回りの状態こそが、「私の心」の投影と分かります。だからこそ、身の回りの整理整頓こそが、自身の心磨きに成るのだ。ああ、そうだったのか。日光で先生から言われた一言が、またここで起動したのです。

可睡には、東海道一の禅の修行道場である「可睡斎」が在ります。此処は、悠久六百年の歴史を刻む、徳川家康公が名づけた古刹。現在は、曹洞宗・専門僧堂として多くの雲水(修行僧)が修行をしています。当日は、この「可睡斎」も案内していただき、午後の温かい陽だまりの中で、美味しい精進料理をいただき、寺院内をゆっくりと見学いたしました。紅葉がとても美しく、この世のものとは思えない風景と建物の中で、本当に「居睡り」をしたく成る様な場所でした。数人の僧侶の方が、場内をホウキで掃いていました。とても静かでした。同じ日本なのに、どうしてこんなに違うのだろうか。場所のエネルギーとは、きっと在るのだろう。可睡には、ほんの半日しかいませんでしたが、古代日本の太古の風と風景を感じました。
前回のブログで紹介した映画「かぐや姫の物語」からも、そのような太古の風を感じました。「竹取物語」とは、平安時代に書かれた日本最古の小説(しかも、SF小説)です。映画の画面からも、日本の原風景の「風」あるいは「匂い」を感じます。それらは、きっと今の日本でも(本当は)感じられるはずのものです。その「感じられる」感性をいかに呼び戻すか。そのスタートラインこそが、「身の回りをキレイにすること」あるいは「大自然や両親に感謝すること」ではないでしょうか。映画「かぐや姫の物語」の主題は、人生讃歌であり自然讃歌です。「生きている手応え」や「生きる喜びと幸せ」を感じたい。それは苦労を乗り越える経験からしか得られない種類のものです。かぐや姫は言います。「私は生きるために生まれてきた」と。かぐや姫は、鳥や虫や獣や草や木や花を愛し、あらゆるものを大切にしていました。育ててくれた両親(翁と媼)への感謝も、最後の最後まで忘れませんでした。乗り越える為に必要なものとは、いつの世でも「感謝」と「清浄感」ではないか。
丸二の理念の基本は「自然の恩恵への感謝」です。現場の基本は「6S(整理・整頓・清掃・清潔・親切・速度)」です。「現場は心の鏡」という合言葉もあります。全てが「感謝」と「清浄感」の追求です。結局のところ、お客様の喜びと幸せ、社員の喜びと幸せを願う時、最後は「感謝」と「清浄感」に行き着きます。そして、そのルーツこそが「先生」の教えでした。私は、亡き恩師への恩返しとして、これら全てを守り続けて行こうと思います。先生、本当にありがとうございました。

※「かぐや姫の物語」ですが、老若男女、全ての方に見ていただきたい映画です。見た方の半数は、「日本昔話みたい。竹取物語そのまんま。特別面白くなかった。絵もそれほどでもなかった」という感想で、もう半数は「何か物凄いものを見た。なぜ竹取物語で号泣してしまったのだろう。涙が止まらない。アニメ史上の快挙。映画史上の大傑作」という感想のようです。私の場合は完璧に後者でしたが、みなさんはどうでしょうか。すでに日本人の誰もが知っているストーリーです。しかもアニメです。ですので、前者の感想の方が(一見)説得力があります。けれども私は後者でした。それがなぜだか未だに頭の中で整理が付かないのです。上手く説明ができないのです。でも、心の深い部分で感じています。多分、きっと・・・生きるために生まれてきたことを、私も「思い出した」のだと。