


2013.04.19

DVDで「ラビットホール」という映画を観ました。ニコール・キッドマン主演で、とても静かで地味な映画です。4歳の息子を事故で亡くした夫婦の物語で、その心の再生を描いたドラマです。けれども大きなドラマ展開があるわけでなく、日々の日常の中で、その悲しみの大きさを(少しずつ)小さくして行く姿を(淡々と)描いています。過去に生きるべきではない。でも明るい未来を描くこともできない。だから今を生きる。ほんの少しの先だけを見ながら。少しずつ重荷を下ろしながら。
映画の中で、その事故を起こした(加害者である)少年と(息子を亡くした)二コール・キッドマンが会う場面があります。もうそこには答えは無く、何か(良きこと)が生み出される可能性すらありません。でも、二人の心は通い合います。そして少年が描く「コミック」が完成するのですが、その主題は「並行宇宙(パラレルワールド)」。この今の現実とは別の世界が(同時並行的に)存在していて、そこでは私も息子も元気に生きている。きっとそういう世界があるはずだ。
この「パラレルワールド」は、多くの科学者によって研究されています。いずれにしても、「今をどう生きるか」によって、複数の未来への可能性が(今、同時並行的に)発生しているという意味においては、理解できると感じます。悲しんでいる自分がいる世界から、幸せな自分がいる世界へ移動すること。それは物理的に移動するという意味では無く、自分自身の意識を動かすことによって、それはきっと可能なことなのでしょう。良きことも、きっとどこかで(同時並行的に)存在していると信じて。
さて、4月13日の淡路の地震以降、三宅島、宮城と続き、同時に海外でもイラン、パプアニューギニアにて大きな地震が発生しました。その間、ボストンではテロ事件が発生し、北朝鮮のミサイル発射問題も収束していない状況です。この短期間でこれだけの重大な事象が起きていることを見ても、世界は「連鎖」していることが分かります。しかしながら「同時並行的」に、きっとたくさんの良きことも起きている「はず」です。何事も陰と陽の両面が在るからです。ただ人間は、どうしても不安と恐れの面だけにフォーカスを向けてしまいます。
例えば、今日(18日)はとても素晴らしい日和で、国分寺市内で地鎮祭を行いました。それはとても「ありがたき」ことです。今日という日が(本当に)やって来て、みんなが(予定通り)元気に集まること出来て、お天道様が暖かく迎えてくれて、無事に立派な祭式を挙行することが出来たのです。何て素晴らしいことでしょうか。でも私たちは、そのような事象を「当たり前」と思い、別の不足面の方ばかりに意識を向けようとします。終わったことを後悔したり、先々のことを不安に思ったり。結局、「いま」「ここ」の幸せを忘れています。これほどもったいないことはありません。
「いま」と「ここ」の素晴らしさに気づき、感謝の心を持って、今、ここで、出来る限りの最善を生きて行くこと。あるいは最善を「生きようとする」こと。その「生きようとする」意識と「動作」自体が、本当の幸せの「正体」のような気がします。世の中で起きている様々なネガティブな現象に意識を奪われたり、いつか来て欲しい物的な(あるいは静止した)「何か」を獲得することに魂を奪われたり・・・。それも確かに必要なことであり、生きるために価値あることですが、「そこだけに」生きてはいけないと感じます。今の自分自身の「良心」が向かっている「流れ」そのものが、私たちの目的(結果)ではないかと思います。
同時並行宇宙があるとすれば、それは自分自身の中に(既に)存在しているのではないでしょうか。だから(一瞬のうちに)どんな世界へも移動できる。確かにそこに、失われた人は(物理的に)存在しないかもしれませんが、「良き思い出と共に在る」という充足と感謝があるかもしれません。今の世の中、いろいろと大変なことが起きていますが、それと同時並行的に起きている「はず」の、たくさんの「良きこと」にこそフォーカスをして、今を思い存分「味わう」こと。そう思えると、今は本当に「素晴らしき世界」です。
2013.04.06
「昨日4月5日の東京株式市場は、出来高が64億4912万株と過去最高を更新し、前日比199円10銭高の1万2833円64銭と3日連続で上昇。4年7カ月ぶりの高値水準となった。」
私の前職は証券会社でしたので、出来高64億株という数字がいかに物凄い商いの量であるか判ります(当時のバブル時でも20億株台だったと記憶します)。当時は取引所内で、大勢の場立ちが手でサインを送りながら、売り買いをしていました。商いが多い日の盛り上がりは(それはそれは)大変なもので、出来高20億株を超えた日などは、当然株価も高騰し、取引所内も異様な興奮状態に包まれ、あちらこちらで拍手と歓声が湧き起こり、ある種の興奮状態でした。日々、投資家にもそのような(取引所の)熱気が伝播し、株価は更に上昇し続け、遂にバブルが発生しました。後にそれは終わってしまうのですが、日本経済が最も光り輝いていた良き時代だったのは事実です。
現在の取引所は全てがシステム売買に成り、もう場立ちの姿はありません。人間の手では無く、機械ですので、64億株も楽に処理できるのでしょう。静かにで効率的で合理的に成りました。けれどもそこには、あの時代の「熱気」はありません。バブル自体に対する見方は様々ですが、あの時、あの場所で、確かに日本は「元気」を創造していたと思うのです。
あらゆるものが効率的、合理的に成り、物事は早くて楽に成りました。便利に成ることで、人々の暮らしはきっと良く成るはずだと。けれども便利と引き換えに、同時に何か大切なエレメントも喪失してしまったような気もします。例えば、連日、証券取引所を包み込んだ「熱気」もその1つでしょう。アベノミクスと日銀の金融緩和政策によって、日本がデフレからの脱却を目指す中、市場が良い反応し始めています。これを発展的に持続して行く為に必要なことは、日本人一人ひとりの気持ちが、前向きに成り、元気に成り、勇気が出る、そういう「気」を創造することではないでしょうか。
いま私たちに必要なのは、「明るい気」です。目指すべきは「北極星」です。「決して手は届かないけれど、あの光り輝く星を目指して行こう」とするワクワクしたビジョンです。北極星とは、常に北天の中心に在る、決してブレない(目指すべき)光点です。そこへ向かう「気」の伝播こそが、日本人の底力を復興させ、(そしていつか必ず)あの北極星のように世界を照らすことを実現するでしょう。北極星に向かって歩いて行こう。世界を照らす場所へ行こう。日本人の潜在意識が、そのような精神の復興によって、一致団結するように思えて成りません。
あの東日本大震災と共に、日本の大地と海は大きく振動しました。けれども、その振動が最も揺らしたかった対象は、私たち日本人の魂だったのでは無いでしょうか。日本人の魂は、共に協力し合う「共認」によって、再び光り輝きます。そこが西洋の個人主義とは違うところです。「みんなで良くしよう」とする共認の和を増幅させることで、震災の傷跡を再生の力に変換する。だからこそ、みんなを照らす北極星に成ろうと。自分だけが良く成るのではなく、みんなで良く成ろうと。そういう意識の方向性が明確に成った時、日本人の「気」は(一気呵成に)一体化すると思います。そしてその力は世界へと伝播して、きっとそこから新しい(熱気に満ちた)社会が始まると思います。だから先ずは、自分自身が北極星に成ること。まわりの人を照らすこと。その総和が、きっと世界を変えると信じて・・・。
2013.03.13
2011年3月11日から丸2年が過ぎ、その日の午後2時46分には(心の中で)黙祷を捧げました。ここ数日、各テレビ局では震災についての特集番組を組み、被災された方々のその後を放映していましたが、(実際には)そこには映らない(映せない)本当の苦しみが未だ存在しているはずだと感じます。被災地の復旧・復興は遅々として進んでいないようですが、確かに、物理的な面において、あの日以前の状態に戻すのには、相当の時間が掛かるのでしょう。さらには以前の場所に街を再現するのではなく、別の地域(高台等)への移設ですから、全てがゼロからのスタートです。作業以前に先ずビジョン(方針)を確立しないと、なかなか心も形も1つに成りません。今までの場所への愛着と共に、またいつか来るかもしれない地震や津波への恐怖の中で、答えの無い質問が(頭の中で)繰り返されている人もいると思います。その精神的な苦しみは、きっと計り知れないものだと思います。
そのような中でも、働く場所がある人は、前向きに生きているように感じます。自分の家を失い、大切な家族を失っても、今日の「衣食住」があり、今日の仕事がある人は(大変な苦しみや悲しみを抱えながらも)生き生きとしているように見えます。もちろん明日への不安を拭い去ることは出来ないと思いますが、「今を生きる力」とは、本当に物凄いものだと感じます。それにひきかえ私たち多くの人間は、毎日「衣食住」に恵まれているのに、常にいろいろな不満や不安を持ち、今を生きずに、過去(後悔)や未来(不安)の中を生きています。終わったことにクヨクヨしたり、まだ来ないことを不安に思ったりして、今の意識が「今、ここ」に無く、どこか遠くに浮遊しています。多分きっと、これほど「もったいない」ことは無いのでしょう・・・。
現在、過去、未来とは言いますが、それは理屈の世界で、実際には(この世界では)「今」しか無いようです。「今」の連続が、ただ続いているだけです。「過去」の経験によって「今」が在り、「今」の意識と行動によって「未来」が形成されます。つまり今の中に、(すでに、同時並行的に)過去も未来も含まれていると言うことです。だから「今、最善を生きる」こと。将来への不安で、今が楽しくないとしたら、それは無意味なことです。今を楽しむことで(同時並行で)良き未来が形成されるからです。同時に、過去の全てに感謝すれば、今を楽しむことも出来ます。今、感謝の心で、最善を生きること。私は、今回の東日本大震災で、そのようなことを感じ、学ぶことが出来ました。
さて今日も強風が吹いています。先日の日曜日には煙霧が発生し、空が急に暗く黄色に染まり、ある種の恐怖心を抱きました。最近は寒暖の差が激しく、花粉の猛威も増して来ています。全て、自然界に対する(私たち人間の)行いの結果だと思います。そうであるならば、私たちは意識を変えて(できる限り)自然を破壊しない生き方に修正しなければ成りません。同時に(その間)自然の猛威から身を守ることも考えなければ成りません。それは「衣食住」の確保が基本であり、特に食糧の確保と安全な住宅が最優先に成ると思います。過去の行いによって、私たちは厳しい(今の)時代を生きていますが、そのことに(積極的に)感謝することで、明るい未来を引き寄せると思います。インフレ、円安、消費税アップ、外交、防衛、原発、エネルギー、社会保障、景気回復、財政再建等、難問ばかりの日本ですが、それでも尚、生かされている現状に感謝して、近隣諸国との融和を思い(願い)ながら、最善を生きて行きたいと思います。そのことが、東日本大震災でお亡くなりに成られた多くの方々への最大の供養だと信じます。
2013.03.08
今週の火曜日は縁会でした。縁会と言っても宴会ではなく、全社員が月1回集まる縁会です。私はここで毎月30分ほど社員さんに話をします。今月は、このような話をしました・・・。
最近は隕石や気球の事故があり、地元では恐い事件が発生し、北海道では暴風雪で多くの方々が亡くなりました。特に地元の事件と北海道の件では、親の気持ちを考えると、何とも言いようのない悲しみが襲って来ます。北海道の暴風雪で9歳の娘を抱きながら亡くなった父親の愛情を思うと、涙が出て来ます。父親は亡くなりましたが、娘は生きることができました。父親は自分の服を娘に着せて、さらに雪から守るように娘を抱いていたそうです。お母さんは数年前に病気で亡くなり、父と娘のたった二人の家族でした。娘は両親を失いました。立派に生きて欲しいと祈ります。
宮澤賢治の物語は、自己犠牲を描いています。「銀河鉄道の夜」では、川に落ちた友人を救うために(カンパネルラが)水に入り、「グスコーブドリの伝記」では、寒波から人々を救うために(ブドリが)火山へ入ります。生と死とは一体何だろうか・・・。「雨ニモマケズ」の最後は、「ヒドリの時は涙を流し、寒さの夏はオロオロ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、ほめられもせず、苦にもされず、そういうものに私は成りたい」と結ばれます。
一般的には「デクノボー」は、「下手」とか「役に立たない」というマイナスのイメージがありますが、賢治の言う「デクノボー」とは、むしろ「自分を後回しにする」あるいは「自分を勘定に入れない」という精神面を強く感じます。現代社会の中では、全く損な生き方であり、決して「成りたい」イメージでは無いでしょう。もう少し深く考えると、それは「愚直」という言葉なのかもしれません。私たち日本人の精神的美徳でありながら、随分昔に忘れ去ってしまった・・・愚直さ。今、東日本大震災を経て、その心の復興が始まっているような気がします。
そう・・・もう「3.11」から丸2年です。時代が大振動を始めて、賢治の理想郷とする<イーハトーヴ>への道が始まりました。振動は大地を揺らすと共に、人々の魂も揺らし続けています。きっといろいろな不都合も起きるでしょう。それでも人間は、前へ向かって歩き続け、きっと乗り越えて行きます。丸二も、賢治の言う「デクノボー」的な面がある会社です。このデクノボー、つまり「愚直さ」を「あきらめない」限り、私たちはこの大振動時代に応援されると思います。
大振動の時代は、大地も空も揺れます。自然現象も揺れ、気候も揺れます。今までの感覚では理解できない天候を経験するかもしれません(先日の北海道のように・・・)。同時に、ますます「衣食住」への重要性が高まると思います。衣食住とはまさに「生」の原点です。あの暴風雪の中、もし(もう一枚)温かい服があったら、もし何か食べるものを持っていたら、もしどこかの建物に中に入れたら・・・。衣食住への回帰、つまり生命を守る産業への回帰は、人間の生きる力の再生であり、あらゆるものの根源への収束を促すと思います。
中でも建設業の存在は重大です。地球環境の変化に従って、自然界の猛威が増すことで、「住居」にも大きな変化が訪れるでしょう。文字通り「生命を守る」ことが中心軸と成るはずです。今現在の建設業界は、様々な構造的な問題が重なり、改善の足取りは遅い状態です。それでも世の中は、かつて無いほどに、建設業を離さなく成るでしょう。決して楽な道ではありませんが、決して失われない道でもあります。
あの北海道の暴風雪の中で、自分の命と引き換えに娘の命を救った父親を思う時、私には(その娘を抱きかかえている姿こそが)建設業の心と感じたのです。何があっても、どんなことをしてでも、守る。人々の日々の生活、暮らし、家族の生命を守る。これが住居の本質だと、気づかされました。だから私はいつもこう言い続けています。「建設業は尊い仕事、聖職である」と。
デクノボー(愚直)を続けて行く限り、私たちの職業は求められるでしょう。もちろん苦労もあるし、評価されないこともある。けれども、それでも良いじゃないか。みんなにデクノボーと呼ばれ、ほめられもせず、苦にもされず、ただ造った建物をギュッと抱きしめ続けるのみ。北の暴風雪の中で、あるいは夜の街の中で、大切な命が失われた時も、私たちはこうして服を着て、ご飯を食べて、家に暮らしている。その幸せへの感謝を決して忘れてはならない。この聖なる建設産業に従事している喜びを持って、明日もまた「良き建築」を社会へ提供して行こう。それが私たちの使命。この道を行こう。
・・・以上が、社員さんへ話した(大まかな)内容です。これからの建設産業で最も大事なことは、熟練技術者を大切にすることと若い力を結集させることです。長年この業界で建築技術の腕を磨いてきた方々の智慧は、国の宝だと思います。もう70歳までは現役の時代です。同時に、その技術の伝承を若い世代へつなげなければ成りません。そのような業界の構造的なテーマを持ちながら、愚直に前へ進んで行こうと思います。
2013.02.28
エジプトで気球が爆発・墜落して(日本人を含む)多くの方々が亡くなりました。最近、何かのTVで(どこかの国の)幻想的な朝靄に浮かぶたくさんの気球群を見ましたが、その時「きれいだなあ」と思いつつも、「落ちないのかな。大丈夫かな。自分はきっと乗らないだろうな」と感じたことを思い出しました。今まで安全と信じていたことが、次々と覆される時代。戦争や原発だけでなく、最近では隕石の落下や(火災が発生した)加湿器、そして今回の気球。私たちの日常の安全神話は、(ここに来て)ひとつの大きな節目を迎えたのでしょう。もう一度、安心安全の点検と確認をしなければ成りません。
長い景気の低迷で、安心安全へのコストが削減され、あるいは人間の意識も散漫に成り、さらには自然界の猛威も加わって、私たちを取り巻く社会全体の中で、事故の発生確率は確実に上がっているはずです。これからは何をやるにしても、「もしも」を想定して、リスクに対する強い意識を持って、(そうならないように)準備をする必要があると思います。毎日のことで言えば、(例えば)車の運転ひとつでも、「横から人が飛び出してくるかもしれない」と意識して、スピードをコントロールする意識も大切だと思います。そのように意識すれば、そのようなことは案外起こらないような気もします。
けれども人間は、慣れと同時に、危険に対する意識が薄れてきます。何となく社会全体が大きなシステムとして(順調に)機能して、何事も(特に考えなくても)スムーズに物事が運ぶように成ってしまった結果、人間全体の意識がこの「慣れ」にどっぷり浸かってしまったような気がします。今、そのシステムの中の様々な箇所で、小さなシステム障害が起こり始めています。今はまだ「部分」の障害ですが、これがシステム「全体」を揺るがす根本的な障害にまで発展すると、人間の智慧では何ともしようが無くなります。そう成らないために、私たち一人ひとりが、(自分自身の日常の中で)小さな障害を見つけて、それを(自分自身で)修繕していくことが大切なのでしょう。
つまり、「意識の修繕」ですね。世の中(外側)を変えるのは大変ですが、自分自身の意識(内側)を変えるのは「いま」「ここで」「誰もが」「すぐに」、可能です。社会システムは、結局のところ人間の総意の意識によって構築(設計)されている訳ですから、やはりその根源は一人ひとりの問題だと思います。みんなが「意識の修繕」を始めたら、ものすごい力と成って、次の新社会システムへのリフォームが動き出すような気がします。
「意識の修繕」は、言い換えれば「心のリフォーム」ですね。話は違いますが、私たち丸二も、修繕工事やリフォーム工事に、一生懸命取り組んでいます。「大」を成すには「小」を大切すること。そのような考え方で、建物の完成後のメンテナンスも心から大事に対応しています。いつも感じるのは、私たちが建物の小さな修繕をする時、(多分きっと)同時に「心のリフォーム」も行われているのではないか、と言うことです。まったく科学的な話ではありませんが、でも確かにそう感じるのです。「小」を一生懸命やっていると、必ず「大」も続いて来る。丸二で言えば、新築工事、大型工事も増加して来ています。最近、アベノミクスで景気が回復中と言われていますが、そういうことにも関わらず、私たち一人ひとりが身近な「小」を大切にすることの方が、実は一番確かだと思います。時間は掛かりますが「確か」です。気球の落下事故を見て、あらためてそう感じました。
※AKB48

初めてAKB48のCDを買ってしまいました。でもAKB48を聴きたくてではなく、付いているPV(プロモーションビデオ)が見たくてです。このブログで紹介していた「この空の花 長岡花火物語」の大林宣彦監督が、今回のAKB48の新曲のPVを監督したと聞き、恥ずかしいとは思いつつも、アマゾンで購入です。娘たちにも「信じられな~い」と冷たい目で見られましたが、負けてはいられません。CDは聴かずにDVDだけを観ましたが、このPVは明らかに大林映画で、完全に「この空の花」の続編(関連作品)です(約60分)。間違い無く、AKBファンは「つまらない」「意味が分からない」「何これ」とお怒りのことでしょう。でも私のような絶対に買わない層に買わせたのですから、秋元康さんの戦略は当たりかもしれません。PVのテーマは、戦争、地震、原発(福島)、祈り(長岡花火)、そして子どもたちの未来への夢。映画「この空の花」を観ていない人にはチンプンカンプンでしょう。でも私は楽しめました。歌もなかなか良かったです。いずれにしても、戦争を経験した世代の願いと祈りを、今の(何も知らない)若い世代に伝えて行くことは、絶対に必要なことです。そういう意味ではもうあまり時間はありません。どう思われようと、どんな形であろうと、このようなメッセージを(あらゆる人やチャンネルを使って)発信して行く「覚悟」と「勇気」に私は賛同します。
(余談)AKBのCDは、ジャケットのデザインが数種類あったり、付録(写真)の付いている・付いてないがあったり、一体どのように買って良いのかが分からず大変でした。だからファンは、「全部」買うのでしょうね。すごいビジネス戦略です。
2013.02.21
木造の住宅を建てるにあたり、柱を無垢材にするか、集成材にするかという選択があります。私たちは、基本的に「無垢材」をお勧めしています。集成材の方がコストは安く、構造計算もし易いため、ハウスメーカー等では多く使われています。でも、小さな木材を接着剤で固めた集成材が、実際にどれだけの耐久性があるのかは未だ不明です。家を支える柱の耐久性が、接着剤の性能(寿命)によって左右されることに成るわけです。一方、無垢材は丸ごと一本の「生」の木ですから、(それぞれに多少のバラつきがあるものの)元々「一体化」されたものであり、数十年の風雨に耐えてきた実績があります。特に「芯持ち材(年輪の中心を持った柱等の製材品)」は、年輪の芯が柱の中心にあるため、木の本来の力がそのまま発揮されます。つまり、集成材の家は「接着剤の力」によって支えられ、無垢材の家は「自然の力」によって支えられると言って良いでしょう。私たちは「自然の力」の方が、強くて、丈夫で、長持ちして、体にもやさしいと考えています。
ただ無垢材は高いというデメリットがあります。そこで私たちは、本当に良い木を産地直送で(適正価格で)東京に送るシステムを造りました。それが伊勢神宮の御用材の産地として有名な、岐阜県裏木曽の加子母森林組合との連携事業でした。日本の山を守るには、木を適時伐採して行く必要があります。そうしないと森に光が入らず、木が育たなく成り、山は荒れてしまい、動植物や微生物も住まなく成ります。「良い木の家を造る」ことと「日本の森を守る」ことの両面を目的として、国の農商工連携事業の認定を受け、加子母森林組合と「産直木造住宅事業」を始めて約5年が経ちました。東京に「神宮ひのきの家」を広めたいと言う一心で、今後もこの取り組みを進めて行きます。
加子母は、東濃ひのきの産地でもあり、伊勢神宮の御用材の山(神宮備林)に指定されています。加子母のひのきは、本当に見事な独特のピンク色で、香りも良く、実際の強度も高いものです。寒暖の差が激しい気候や土壌の良さが、そのような立派な木を育てているのでしょう。加えて、日本全国で有数の森林組合である「加子母森林組合」の山造りに対する情熱と愛情は、とても素晴らしいものです。やはり最後は「人」です。山と自然を愛する人々が、丹精込めて(数十年をかけて)育て上げた「木」が支えてくれる家・・・それを私たちはお客様にお届けしたいのです。今年も加子母森林ツアーを開催いたしますので、ぜひご関心のある方はご参加ください。加子母の山と木と人との出会いが、きっと人生に笑顔と安心を与えてくれると思います。
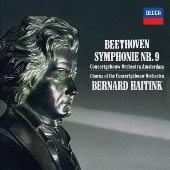
※ベートーヴェンの第九
ハイティンク&アムステルダム・コンセルトヘボウによる1980年の第九ライヴです。約20年振りの再発売とのことですが、いつまでも繰り返し、繰り返し、受け継がれていく芸術は、まさに人類の遺産と言えるでしょう。それでもやはり人間の力は、人智を越えた「自然」の永続性には敵いません。私たちはいつまでも自然界から学び、生かされ続けて行くのだと思います。でも、ベートーヴェンの第九は、人間の力の最高峰の一つだと思います。
2013.02.15
物質をどんどん細かくして行くと、最後は原子と分子の振動(波)エネルギーへと行き着きます。科学的にそう成っています。そうすると、世の中に在る全てのものは振動している(動いている)という理屈が分かります。振動は「波」ですので山と谷が交互にやって来ます。これは、あらゆる事象の雛型に成っていると感じます。人生も同様に、誰もが「山から谷へ」「谷から山へ」を生きています。「山高ければ谷深し」ですから、急上昇は反転すると急降下に成ります。だからゆっくりと上昇をしながら、時に休んで(しゃがんで)、またゆっくりと・・・が良いのでしょうね。仮に下降期にあっても、どこかで必ず底を打って、今度は(必ず)上昇に転じます。その時が来るまで「あきらめずに」努力を続けて行けば良いと思います。どんなに辛いことも、いつかは終わります。逆に良いことばかりも続きません。そういう「波」の上を私たち人間は生きている、否、生かされているのではないでしょうか。
だからこそ、その波に身を委ねつつ、その(山谷の)波長のベクトル方向が右肩上がりに成るように「持ち上げて行く」ことが大切だと思います。山と谷を交互に繰り返しながらも、右肩上がりの勾配を少しずつ昇って行けば、スパイラル状に上昇して行きます。そのような「ベクトル造り」こそが、人生の本当の目的であり、山や谷を無理に補正することで「(目先の)苦労を回避する」ことでは無いと感じます。良い時は良いし、悪い時は悪い。それが自然で良い。そこをあえて補正せず、むしろ良き経験として味わって行く。その実体験の中から、自らのベクトルの角度を1度持ち上げて行く智慧が生まれる。結局最終的には、その方が、ずっと高い場所へ(安心安全に)到達する様な気がします。
自然界の法則は全ての雛型に成っている様です。だから大自然から学ぶことは多いです。私たちは元々自然界にあるものを使わせていただいて、生活をしています。木も、草も、電気も、皆自然界からいただいています。人間はそれらを利用(加工)して様々なモノを造っていますが、その「大元」を造ることはできません。誰も、花の種をゼロから造れません。原子を造れません。自然界の運行システムを開発することはできません。できるのは「発見」だけです。そう思えば、この山と谷の流れのシステムに従って、自然に(あるがままに)生きて行くことだと思います。3.11以降、向かうべき方向はここに在るように感じます。
人生のベクトルを(右肩上がりに)持ち上げて行く。その角度を(少しずつ)付けて行く。それが、私たち一人ひとりのテーマだと思います。それはとても時間が掛かることです。目先の谷を回避する方が手っ取り早くて楽です。でもその補正は後にきっと、さらに大きな谷を出現させるかもしれません。ベクトルを持ち上げるのはとても大変な作業ですが、それでも1度上がれば、その角度は長く保たれ、(時間が経てば経つほど)高い到達点へ向かいます。実は私たちの会社の経営方針も、(波の補正では無く)この角度を「1度」上げることを大切にしています。目先の小手先テクニックではなく、常に根本的な部分を見つめて、時間を掛けて、角度を少しずつ上げて行く。それはとてもとても小さな変化で、ほとんど目には見えません。急成長にも成りません。それでも時間が経つにつれて、一度の角度の差が、いずれは大きな距離の差と成り、はっきりと目に見えるように成ります。木の「年輪」の様にゆっくりと育って行くのです。あらゆる物質が振動エネルギーと知ることで、このような経営方針にも生かすことが出来ます。自然界の摂理は、経営の在り様をも包み込んでいるのでしょう。
音楽も振動エネルギーです。単なる振動エネルギーなのに、人をワクワクさせます。感動させます。悲しくさせます。人間の細胞も元は振動エネルギーだから、きっとお互いが共鳴するのでしょう。自然の摂理とは不思議なものです。ベクトルの角度を1度上げるとは、この自然の摂理を学び、仕事や日々の生活で生かすことではないかと考えています。丸二の経営理念の第1番は、「自然との総和に徹し、自然の恩恵に感謝できる会社造りを目指す」です。これが私たちの最も重要なベクトルです。
※シューベルトの最後のピアノ・ソナタ
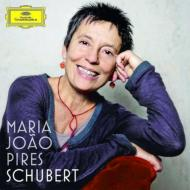
シューベルト:ピアノ・ソナタ第16番、第21番
マリア・ジョアン・ピリス
シューベルトが31歳で亡くなる数週間前に書いた、最後のピアノ・ソナタ第21番。その調べは、まるで冥界の入口に立つ人の心を映し出す「鏡」のように美しい・・・。今から185年前に書かれたこの曲が、21世紀の人々の心を揺さぶるのはなぜでしょうか。振動エネルギーは時空を超えて、生き続けるからではないでしょうか。私たちは「今」という「刹那」を懸命に生きることで、未来へ向けての無限の力を放射し続けていると思います。シューベルトも、あと少しの生命と感じながら、その時(今)を懸命に生きていたと思います。その振動エネルギーの全てが「曲」に記憶されたのでは・・・。「今」を懸命に。それが未来を造る。
2013.02.04
昨夜のNHK・ETV特集で、先日ブログで紹介した冨田勲さんの「イーハトーブ交響曲」の特集が放映されました。タイトルは、「音で描く賢治の宇宙~冨田勲×初音ミク 異次元コラボ~」です。CDを買って以来、(毎日聴きながら)深い深い感動を味わっていたので、もちろん観ました。
冨田勲さんは言うまでもなく、世界のシンセサイザー音楽の開拓者(パイオニア)です。ドビュッシーの「月の光」やホルストの「惑星」等のクラシック音楽を、全てモーグ製のシンセサイザーで演奏するというトンデモナイことを始めました。今から約40年も前にです。それから電子楽器が生まれ、今では様々な音楽に当たり前のように使われています。でも当時は、「機械の音楽なんて邪道」と言われ、冷たい評価を受けていました。それでも自分自身の夢と信念を貫き、こうして時代の先駆者と成ったのです。
番組の中で、宮澤賢治に対する冨田勲さんの思いを聴くと、やはり戦争体験や逆境を生きて来た自身の人生が、その根底にあるように感じました。そして冨田さんが子どもの頃に読んだり、映画で観た宮澤賢治の異次元世界が、それから70年経った今でも、心の中に存在してしたということです。
今回の「イーハトーヴ交響曲」は、シンセサイザーでは無く、フルオーケストラと合唱によるシンフォニーです。そして、競演する歌手が、ヴァーチャルシンガー「初音ミク」。存在しない「人」ですね。その競演作業はとても大変だったようです。実際の演奏は、当然テンポが揺らぎますから、指揮者の棒に合わせなければいけません。初音ミクも同じです。普通なら、すでに録音されている「初音ミク」のテンポにオーケストラが合わすところですが、それでは意味が無い。その時、そこで、初めて「初音ミク」が、一緒に歌うことが重要だったのです。そのような「こだわり」を持って、いろいろな新技術を駆使して、初演の成功と成りました。
宮澤賢治の作品は、何か不思議な異空間を感じます。とても身近で日常の世界を描いているのにも関わらず、その向こう側に4次元世界が横たわっています。その異次元空間を行ったり来たりする存在として「初音ミク」が参加したのでしょう。このような全く新しい発想や挑戦が出来るところが、やはり「パイオニア」なのですね。今の若い世代よりも、よっぽど頭が柔らかくて、勇気があります。
また、私が大好きな詩「雨ニモマケズ」も歌われました。冨田勲さんの意識には、やはり.3.11のことがあったそうです。宮澤賢治のイーハトーヴ(理想郷)とは東北岩手です。その東北の人々への思いこそが、この曲を完成させたのではないでしょうか。「銀河鉄道の夜」は、死者を天上まで運ぶ列車でした。川で溺れた友達を救うために、水に飛び込んで死んだカンパネルラを乗せて、銀河鉄道は宇宙を昇って行きます。それは3.11で亡くなった多くの東北の方々を連想します。世のため人のために、自分自身を犠牲にして命を捧げた全ての人への感謝の祈りです。この「イーハトーヴ交響曲」では、「銀河鉄道の夜」のクライマックスで、子どもたちの合唱が「カンパネルラー!!」と叫びます。それは、今ここで生きている私たちから、あの震災で亡くなった方々への感謝の呼び声と判ります。
「銀河鉄道の夜」の主人公は、カンパネルラの親友のジョバンニです。ジョバンニは、眠っている間、銀河鉄道に乗って、カンパネルラと旅をします。その時ジョバンニは、最も天上に近い駅までの切符を手にしていました。これは一体どういう意味なのでしょうか。ジョバンニは、病弱な母親のために、毎日ミルクを買いに行きます。学校へ行きながら、印刷所で働いています。遠い海で働いている父親の職業のことで、友達からイジメられています。そのジョバンニが、一番良いところまで行ける切符を手にしていました・・・。
イジメが問題に成っている今こそ、あらためて宮澤賢治を理解する必要があると思います。生きることの意味をもう一度、真剣に考える時です。東北で3.11が起き、私たちは気づかされました。だから残された私たちは「反応」しなければいけません。「雨ニモマケズ」の精神は、単なる辛抱の話ではなく、真の「さいわい」への切符でないのかと。その切符を私たち人間は、すでに持っているのかもしれない。だからこそ、今の日常に感謝して生きて行くことが大切だと・・・。
番組のインタヴューの最後で、3.11で亡くなった東北の方々への思いを語る冨田勲さんが、涙をぐっと堪えているのが印象的でした。
2013.02.02
少子高齢化が問題に成っています。若い人が少なく成ると、未来の社会を支える力が不足するからです。国としても少子化対策を行っていますが、その効果が出るのには相当な時間が掛かるでしょう。そう考えると、逆に高齢化社会が生かされるような時代を造って行くことも面白いと思います。
つまり、個人の「実力」が歳を追うごとに上がって行く仕事を見つけることです。働き盛りのピークが60代とか70代、あるいは80代の仕事です。例えばアーティストや芸術家はそうですね。指揮者も60代はまだ若手です。国民が高齢化するほど、実力が上がる国を造るのです。それはきっと健康と長生きも同時に実現できるかもしれません。歳を追うごとに、認められ、評価され、必要とされる社会に成れば、人はもっともっと元気に成ると思います。
そう考えると、建設業は宝の山です。建築技術者が日々の仕事から得ている経験量は、本当に凄いものが在ります。歳を追うごとに技量レベルも上がって行きます。体力的な問題さえ無ければ、年齢的なピークは無く、どんどん右肩上がりです。このような貴重な「智慧」を生かさないのは、社会の損失であり、国家の損失です。
この業界に身を置いて常に感じるのは、ベテランに成れば成るほど「素晴らしい」と言うことです。政治の世界のように、若い世代への刷新が必要なところも多いですが、逆に「年輪を積み重ねたからこそ発揮される智慧」を生かす社会システムも重要だと思います。そのような智慧者を「尊敬する心」が、(逆に)若い世代を育てることに成ると感じます。
建設作業は「自然」が相手です。自然界は未来永劫変わらないものです。であるならば、私たち建設産業人の本質も変わらないはずです。新しい技術やテクニック論はもちろん変化して行きますが、建設作業の原理原則は変わりません。だから、ベテラン建設人の智慧は偉大なのです。私は今48歳ですが、もっともっと多くのベテラン建設人の先輩方と仕事をして行きたいと思っています。確かに柔軟で新しい発想は若手に軍配が上がりますが、建設作業に最も大切なのは「基礎」です。私も基礎を学びながら、新しい発想を目指して行きたいと思います。
※お勧めDVD
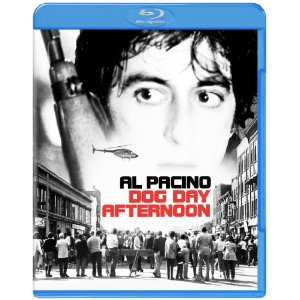
映画「狼たちの午後」
上記の内容とあまり関係ありませんが、最近ブルーレイで観て、あらためて感嘆した映画「狼たちの午後」です。確か中学生の頃に2本立てで観たような記憶があり、その時、ものすごく面白かったという印象がありました。それから数十年振りでしたが、またまた本当に面白かった。「ゴッドファーザー」出演直後のアル・パチーノがとんでもない銀行強盗犯を演じています。実際の事件を再現した物語なので、とてもリアリティーがありながらも滑稽な面もあり、最後までドキドキワクワクしました。このように映画や小説は、時に犯罪や事件を題材にしますが、それは全ての人間の持っている「孤独」にフォーカスするためではないかと思います。この映画の主人公も孤独です。そして私たち人間も、皆「一人で生まれて、一人で死んで行く」孤独の面を持っています。だからこそ、力を合わせて温かい社会を作り、お互いを尊重し合うことを大切にするのだと思います。人が歳を追うごとに評価され、尊敬される社会は、きっと温かい社会だと思います。
2013.01.31
前のブログでご紹介した音楽家の冨田勲さんは、1932年(昭和7年)生まれですので、今年81歳です。また以前紹介した映画監督の大林宣彦さんは、1938年(昭和13年)生まれで、今年75歳です。大林監督は最近、「AKB48」の新曲のプロモーションビデオも手掛けました。政治の世界では「老害」と言われる年代ですが、クリエーターの世界には「老い」という概念は無いのかもしれません。今の若い人たちよりも、よっぽど頭が柔らかく、常に新しい挑戦を続けています。生きたいのに生きられない人がいて、生きられるのに死のうとする人がいる世の中で、歳を重ねる度に「生きる力」を加速させている人もいる。古き日本と新しき日本の2つの時代を駆け抜けて来た世代の凄みを感じます。
その「生きる力」の源泉は何だろうかと考えます。戦後の苦しい時代を生きながら、何か「とてつもない」大きな夢を抱き続けて来たのではないかと想像します。あまりにも苦しかったからこそ、「無限の夢」を持ち続けるしか生きる術が無かったのではないか。もしそうであるならば、現代の子どもたちは、中途半端な幸福の中に居て、「無限の苦しみ」も無い代わりに、「無限の夢」も無く、毎日同じ安全地帯を、ただ浮遊しているだけなのかもしれません。
宮澤賢治は、今で言うところの「スピリチュアル」な人間だったと思います。しかし、宮澤賢治ほど、現世において必死に生き切ることを実践した人はいません。今流行りのスピリチュアルのような浮遊した自己逃避では在りませんでした。常に現実の生活の中に、悩みや苦しみ、悲しみがあり、それを具体的に乗り越える実体験の中から、物事の本質あるいは精神性に肉迫して行ったのでしょう。冨田勲さんも大林宣彦さんも、宮澤賢治の次の世代ですが、「戦争」という「苦」の実体験を乗り越え、生き延びることが出来た分、感謝の心で「生」を謳歌し続けているのではないかと思います。
やはり、感謝の念が基礎ではないでしょうか。生きていること、生かされていることへの感謝の念の強さが、その人の人生を最終的に決定していると思います。素直な心で苦労を体験した人が最後は幸福に成るのも、そういう道理からではないでしょうか。これから、また苦労の時代が始まりそうですが、でもかつての戦時中に比べたら、まだまだ本当に幸せです。そのありがたみを感じながら、私たちも歳を重ねる度に、ますます「生きる力」を加速させて行きたいと思います。
※お勧めDVD

大林監督の映画「その日のまえに」。以前紹介した「この空の花 長岡花火物語」の1つ前の作品です。この映画も常識に囚われない摩訶不思議な作風で、賛否両論ありましたが、私は大好きです。映画の本筋と並行して、宮澤賢治と妹トシとの物語が重なり、最後は「銀河鉄道」と「花火」で昇華されます。この花火がきっと次の「この空の花」へ受け継がれたのでしょう。心静かで温かい映画です。「生きる力」の映画です。涙が止まりません・・・。