


2010.12.08
21世紀に入って、早くも10年が終わろうとしていますが、これはオペラで云うところの「前奏曲」にあたり、いよいよ来年から「第一幕」が始まります。前奏曲は、これから始まるドラマや登場人物を暗示させるモチーフで構成され、それを聴くことによって、オペラ全体の印象が解かるものです。
ドイツが生んだ巨大な作曲家リヒャルト・ワーグナーのオペラ(楽劇)の数々の前奏曲は、それ自体が無限旋律の大河であり、壮大で深遠な物語を予感させるものです。有名な楽劇「ニーベルングの指環」は、極めて特殊な作品で、上演に4日間掛かります(約14時間)。序夜「ラインの黄金」、第一夜「ワルキューレ」、第二夜「ジークフリート」、第三夜「神々の黄昏」という4つの作品で構成され、序夜「ラインの黄金」が前奏曲的な位置付けとなっており、この壮大な物語の起点・原因を示し、すでに結論を暗示しています。
さて、そうなると・・・「21世紀のための前奏曲」を(10年も掛けて)聴くことができた私たちは、これから始まる「第一幕」「第二幕」「第三幕」を暗示(予感)させる出来事に、すでに出会っているわけです。であるならば、おそらく「大変革」となるであろう21世紀の方向性は、見えて来たと思います。
「資本主義が終わり、何か新しい社会システムに変わりそうだ」「エコロジー、環境、自然との共生の時代になる」「インターネット、IT、情報革命がもっと進む」「癒し、健康、精神世界が最大のニーズになる」「農業、林業、第6次産業が花形産業になる」「医療技術の進歩」「国や政治が弱体化し、個人の時代になる」「テロ、紛争、政情不安は終わらない」「異常気象、天災地変の多発」「宇宙開発の進歩」「量子力学、新しい科学の時代へ」「戦争経済VS共生経済の戦い」「円高・ドル安」「中国・アジアの時代」「日本食ブーム」「木・水の時代」「教育の問題」「宗教から信仰へ」「真の幸福の追求」・・・。
この10年間を思い起こすだけで、多くのキーワードが頭に浮かびます。良いこともあれば、悪いこともあります。ただ思うのは、世の中は間違いなく「良くなっている」と云うことです。確かに日々のニュースだけを見ていると、悪いこと、凶悪なことばかりが起きているように感じます。でも、だからと言って、(戦国時代と比べて)(龍馬の時代と比べて)(二つの世界大戦の時代と比べて)(戦後復興の、物が無い時代と比べて)今がどうかと言うと・・・今の方が明らかに豊かで幸福です。良い時代です。
それなのに、私たちは不平不満を言う。戦乱の時代を生きていた人々にしてみれば、「今がどれほど幸福か!」ということだと思います。ですので、この「21世紀のための前奏曲」には、何か面白い仕掛けがあるように思うのです。つまり、この曲の中に含まれた多くのモチーフの中で、プラスの曲調に意識を合わせるのか、マイナスの曲調に意識を合わせるのかで、その後のドラマ全体のストーリーが(個人単位で)変わってくるような気がするのです。
聴衆の全体意識によって物語の筋が変わるなんてことは、通常の上演ではありえません。また、観る人ごとに筋が違うことも、ありえません。でも、この「21世紀楽劇」では、そのような(変な)仕掛けがあるかもしれません。であるならば、今起きている事象(世界単位でも、個人単位でも)の中で、「いいなあ~」「楽しいな~」「すごいな~」「面白いな~」「素晴らしいなあ~」と思えることに意識をフォーカスして行くと、面白い21世紀物語が生まれそうです。
私たちは、そこを試されているような気がします。一見、困難に見えるようなフル・メニューを前に出されながら、それをいかに美味しい味に変えてしまうか。この10年間の前奏曲は、困難の「てんこ盛り!」でしたから。だからこそ、きっと、そのような仕掛けが隠されているんだと思います。
今、お笑いが流行っているのも、ある意味、「嫌なこと」「つらいこと」を、「笑い(というプラス側)」に転換させる技術が(無意識に)求められているからかもしれません。重い病気の人が、落語や漫才、お笑い芸人のショーを見て大笑いしていたら、病気が治っちゃったという話もよく聞きます。
このようにして、「21世紀のための前奏曲」は、そろそろ終演です。そして、暫しの休憩の後、いよいよ「第一幕」が始まります。笑いでいっぱいの喜劇になるか、戦いの大スペクタクルになるか・・・。丸二の私たちは、豊かさと幸福感で満ちた、温かい「建築造り」の物語を生きて行こうと思います。
2010.11.23
「新しい段階に入った」・・・何かそう思わざるを得ない数々の事象が、次から次へと続出し、世の中が右往左往しているように見えます。その1つの象徴としては、何事も「長続きしない」ということがあります。総理大臣にはじまって、ヒット商品から芸人さんまで、とにかく目まぐるしく入れ替わっていく。
時代がすでに次の段階に入ってしまっているのに、まだ以前の意識・やり方・考え方では、もう本流になることが出来ない。だから、今までの勢いで(一時的に)勝利しても、すぐに(短期間で)落ちてしまう。
このように、せっかくの努力が水の泡になってしまわないように、私たちは、まず時代の変化・変革の様相を正しく理解して、この21世紀の新しい段階に相応しい人造り、会社造りを行い、持続可能な社会・経済・会社・地域・環境を造っていく責務があると思います。
私は今、46歳。数百年に一度の大変革を、人生の30代の頃から経験し始め、40代でさらなる荒波と向き合い、そして50代(60代かな?)では(きっと)未知なる新世界を見ることになるでしょう。そのような奇跡的な激動との「縁」をいただき、この時代を生かされていることに対する畏敬の念、感謝の念、驚きの念を隠すことができません。
最近、小中学時代の多くの友人たちと再会する機会が急に増えてきました。それぞれ、全く違う道を歩みながら、当時の良き思い出を共有する友人たち。東京オリンピックの頃に生まれ、高度成長の波に乗って、(親の世代のおかげもあって)物質的な豊かさを享受しながら、成長してきた世代。それが社会に出た途端、ブラックマンデー、阪神大震災、リーマンショックを経験し、やっと社会を牛耳ることができる年代になった今、このような混沌とした世の中にいる。
でも、まさに、このような時代と正面からぶつかったのは、「我が世代」こそが、この混沌を解決できる大きな底力を持っているからではないかと、思うのです。ITブームの頃は、私たちよりもずっと若い世代が、先に世に出ました。でも、今は静かです。私たちよりもずっと上の世代は、戦後の厳しさを乗り越えて、良き時代の波に乗って行くことができました。そこで、残されたのは・・・我が世代(40代~50代)です。
さあ、いよいよ出番でしょうか。小中学時代の友人たちは、みんな元気です。様々な経験(苦労)が血となり肉となり、もう何かをしたくて堪らないようなエネルギーに満ちています。多分(きっと)、我が世代が新しい社会を築きます。新しい段階に相応しい世の中を造ります。もしそうであるならば、間違いなく素晴らしい共生の社会になります。
なぜかと言うと、我が世代は、(良い意味で)昭和の古き良き世代と、新たな新人類との間に立っていて、とても穏やかで温かくて中庸な精神性を持つ人たちが多いからです。努力を大切にして、上昇志向を持ちながらも、競争だけを美徳とはしません。喧嘩はありましたが、陰湿なイジメはありませんでした。皆、お互いの個性を認め合い、自然体で一緒に生きていました。
だから・・・本当に豊かで持続可能で、皆が精神的に幸福感を持つことができる社会を造ることができると思います。私もその素晴らしい世代の一員として、これからも出来ることをやって行こうと思います。そして50代(~60代)になった頃には、「やっぱり日本ってすごいなぁ~」という時代にしていきたい。今はただ、そのような「志」を持つことが出来る人造り、会社造りを目指すのみです。
2010.11.04

11月に入り、今年もあと僅かになってきました。気候の方も、寒暖の差が激しくて、毎日の服装選びが大変ですね。それでも季節は(当然のごとく)冬が来て、そしてまた春がやって来ます。山高ければ谷深しで、季節や人生も、このような幾何学的な曲線を描いて時間と共に移り変わります。多分、そのような自然の法則を変えることはできないのでしょう。
でも、その曲線に右肩上がりの勾配を付けてあげることは可能ではないでしょうか。もしそうなれば、人間はこの「山(いいこと)」と「谷(わるいこと?)」を行ったり来たりしながらも、気が付いたら、スタート地点よりも高い位置(目標とか幸福)へ上昇していることになります。
そうなると、勾配の角度をプラス側にしなくてはなりません。角度がゼロですと、ずっと横ばいですし、マイナスだと悪化して行きます。どのようにしたら、プラス側にできるのか・・・。
数日前、NHK-BSで、スティーブ・マックイーンの特集をやっていました。私が子供の頃に最も好きだったスターは、実は「スティーブ・マックイーン」。部屋に大きなポスターを貼ってました。今の若い人は、知らないかもしれませんね。どちらかと言うとアクションスターとして人気がありました。
私が好きな作品は、「荒野の七人」「大脱走」「ブリット」「華麗なる賭け」「パピヨン」。そして大ヒットした「タワーリング・インフェルノ」。この超高層ビルの大火災を消す消防隊長役は、最高にカッコよかったです。
でも、今回のBSのドキュメンタリーを見て、あらためて彼の人生の壮絶さを知りました。父親に捨てられ、叔父の家に預けられ、農場で働き、その後不良となり、少年院へ入る。その後、役者を目指し、ハングリー精神むき出しにして、主役を勝ち取っていく。「タワーリング・インフェルノ」では、とうとう大スターのポール・ニューマンを超え、名実ともに成功しました。
ところが彼は、その後いよいよこれからという時に、多くの有名作品の出演依頼を断り、田舎に入ってしまう。3番目の妻と一緒に、農場をつくり、長い旅に出る。そこでは俳優スティーブ・マックイーンという顔ではなく、普通の一般人としての生活だったようです。高級なホテルやレストランは嫌がり、普通の宿、普通の店に行き、普通の人々と話をする。
結局、最後は病魔に侵され、50歳で亡くなってしまうのですが、それまでの間、有名人になったにも関わらず、かつて入所していた少年院に行って、そこにいる少年たちと触れ合い、励まし、元気づけていたそうです。
子どもの頃、両親の愛を受けることが出来なかった時に、叔父の農場で畑仕事をしていた事が一番の幸福だった・・・スターとして成功しても、彼にとっての真の喜びは、そのような普通の生活の中にあったのかもしれません。私がかつて、スティーブ・マックイーンに魅かれたのは、何かそのような目に見えない、内面的な深みを感じていたのかもしれません。
人生をより良く生き、少しでも高い位置に到達するには、他者からどのように思われるかではなく、自分自身がどうしたいか、どうなりたいかではないかと思いました。その意思が、右肩上がりの勾配を支えるのではないかと。その意思さえあれば、どのような険しい山も谷も、勇気を持って超えられるし、そこから様々な学びを得て、気付くこともできる。人生とは、人それぞれの山と谷を超えながら、本質に迫っていく旅なんだろうと、感じました。
2010.10.13
先週の10月8日、おかげさまで丸二は、創立57周年(58年目)を迎えることができました。これも永年にわたるお客様並びに関係各位皆様のご愛顧の賜物と、心から感謝いたします。本当にありがとうございます。
また、私が先代より事業継承をしてから数えると、この日でちょうど丸13年となります。その間、時代の急激な変化の中で、本当にいろいろな経験をさせていただいていますが、今になって、つくづく「幸せだなあ」と感じています。
「こんな経験が出来た。こんなことが解った。こうしたらダメなんだ。こうしたらきっとうまくいく」・・・このような多くの気づきの連続の中で、生きていくための智慧(=無形の財産)を日々習得することができているからです。これほどの価値と喜びは、きっと他には無いでしょう。
私が思うに、建築はまだまだ未開の産業で、本当に進化発展するのは、まさにこれからではないかと思います。都会の中で、ビルやマンションを建てるにあたり、「ルネス工法」あるいは「外断熱工法」等がどんどん普及していけば、建築がそもそも持っている潜在能力が、今までの数倍以上に拡大していくはずです。
日本という土地(=空間)が小さな地域・場所において、いかに空間を有効活用し、それを大切に維持し、かつ快適な環境にしていくという取り組みは、国としても個人としても、極めて重要なことではないかと思います。しかもその問題を、建築の技術によって解決することができたのであれば、まさに「建築革命」の到来です。
「ルネス工法」あるいは「外断熱工法」を先駆けて取り入れられた、多くのお客様の建物を日々施工させていただきながら、私たちは、このような新しい建築の「文化的・歴史的価値」というものを(決して大げさではなく・・・)感じます。これからは、今までの常識的な空間というものに、さらなる付加価値を加えていくことが、建築の世界では必要なことですし、(また逆に)この産業にはまだそれだけの余地(未開地)がたくさん残っているということです。だから、建設業ほど夢のある、未来型の成長産業はないと言えます。
また、ビル・マンションの建築において、コンクリートの品質に対する人々の意識もまだまだ低い状態です。これが、日本の建物の寿命を短くしている1つの大きな要因ですので、まず人々が、コンクリートの品質に対して関心を持って、意識することです。それによって、造り手の意識も変わります。当社の「パワー・コンクリート工法」に関心を持つお客様が増えてきたのは、社会を変えるひとつの素晴らしいシグナルだと思います。
また、物理的な空間活用法と共に、精神的に良い作用を及ぼす空間造りも大切です。なぜかと言うと、多くの建築空間は、人々が幸せに暮らしたり、仕事をしたりするためのものだからです。実はその根本的・本質的目的が、今の建設産業からは、欠落しています。ただ、物理的にモノを建てるだけでなく、その建築(家、住環境、職場環境)が、何のために造られようとしているのかを理解し、その真の目的に適う「場」を造ることが重要なのです。
「自然素材」や「建築医学(風水環境科学)」への取り組みは、そこに住み、暮らし、働く人たちが、快適で、楽しくて、健康で、幸せで、豊かな感情を獲得するためのものです。建築(場)によって、人は健康にもなるし、病気にもなります。楽しくもなるし、つまらなくもなります。プラス発想にもなるし、マイナス発想にもなります。つまり・・・建築によって、人の人生(考え方、感情、気持ち、判断等)が大きく左右されるという面があると言うことです。
そのような具体的な中身までをも理解して、建築に取り組むことができれば、いよいよ「建築革命」が始まります。日本の貴重な(希少な)空間を様々な技術・工法で大活用し、心と体がより良くなるような場を造る。それは、その人の人生までを変えて行く。さらに、同時に自然・環境にも貢献する。
丸二は、以上のような包括的な建築を考えて、微力ながらすでに「建築革命」を始めています。最近、成長し始めている「加子母ひのきの産地直送・健康エコ住宅」も、その中で大切なピースの1つです。建設会社と森林組合が「直結」するという、今までの常識を超えた取り組みの下地には、このような「建築革命」への思いがありました。
さらに、「コーポラティブハウス」への取り組みも、「これからの街づくり、地域コミュニティー造りには、建築の介在が必要不可欠である」という先駆的な発想に共感したからです。「コーポラティブハウス」の施工上の苦労は当たり前のことで、それ以上に、この「コーポラティブハウス」の持っている役割、使命感に共鳴したのです。まさに「建築革命」です。
また、現在積極的に取り組んでいる「リフォーム事業」についても、金額の大小よりも、多くのお客様とのご縁を結ばせていただき、さらにそのご縁を深く長く育み続けて行くことを主眼にしています。「住みたい街№1吉祥寺の建設会社」として、ほんのちょっとの事でも、気楽に頼める安心の建築屋さん(リフォーム屋さん)も、街にとって貴重な存在です。
私たちは、常にお客様の身近な存在として、24時間お客様をサポートすると共に、様々な技術・工法によって「最良の建築」をご提案していきます。それが、私たちの「建築革命」であり、大きな夢です。そして、このような夢を持てていること自体、「幸せだなあ」と感じる今日この頃です。
※幸せを感じる音楽
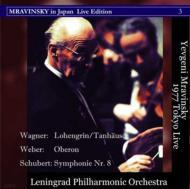
シューベルト:交響曲第8番《未完成》
ワーグナー:ローエングリン第1幕への前奏曲、タンホイザー序曲
ウェーバー:オベロン序曲
ムラヴィンスキー(指揮)&レニングラード・フィル
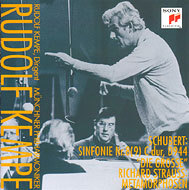
シューベルト:交響曲第9番《グレート》
Rシュトラウス:《メタモルフォーゼン》
ケンペ(指揮)&ミュンヘン・フィル
今まで、あまりシューベルトは好きではなかったのですが、最近やっと良さが分かるようになってきました。そのきっかけは、ムラヴィンスキー指揮の1977年東京ライブでの「未完成」です。とても何か深いところから湧き上がってきたような演奏で、ある種の恐さ(と言うよりも畏怖の念)もあるのですが、この音楽の面白さ(深さ)を実感することができます。私にとって、初めて「未完成」で感動した演奏です。
また最近では、ケンぺ(指揮)の「グレート」を聴き、これもこの曲の持っている冗長さを感じさせない「美しく躍動する音楽」で、とても気に入りました。何か嬉しい気持ちにさせてくれる演奏です。
シューベルトを聴くと、とても静かで穏やかな気持ちになります。今のような騒がしい世の中で、心豊かに生きて行くためには、たまにはシューベルトもいいなと思いました。
2010.09.24

最近スカパーで、映画「ナポレオン」を観ました。これは、アベル・ガンスという監督が1927年に撮った、かなり古いモノクロ無声映画(オリジナルは12時間)で、80年代に映画監督フランシス・コッポラが4時間に再構築し、コッポラの父親(カーマイン・コッポラ)が音楽を付け、フルオーケストラの生演奏による上映会を行った巨大な作品です。実は私も、当時それを観に日本武道館まで行きました(確か、高校生の頃だったと思います)。
「無声映画+生オーケストラ演奏」という経験は、いまだにこの「ナポレオン」しかありません。今回、スカパーで録画したものを、少しずつコマ切れで観ながら、あらためてこの作品の物凄さを実感しました。
武道館での上映会の時に一番驚いたのは、映画の最後の方で、別の2台の映写機が同時に回り出し(合計3台の映写機となり)、スクリーンが「左」「中」「右」と3つに広がり、それらが(きちんと繋がった)一つの場面を映したり、別々の3つの映像を映したりしたことです。この迫力は大変なものでした。また、3つのスクリーンの着色が、「青」「白」「赤」と、フランス国旗を表現していました。
実は、武道館での上映会で(私が行った日は大丈夫だったのですが・・・)映写機がうまく回らないというアクシデントもあったようです。映写機を同時に3台回すようなことは通常あり得ないことですので、妙に納得した覚えがあります。
この3画面シーンは、スカパーの放映では、全体を縮小して(小さく)画面に納めていました。映画館ですと、スクリーンが突然3倍になるわけですので、その衝撃の違いは確かにあると思います。
さて、この映画では、その他にもオーバーラップや画面分割等、当時の技術を大きく跳び越えた手法がたくさん取り入れてあり、「本当に80年前の映画なのか!」と、びっくりです。映画のオープニング(ナポレオンの少年時代の雪合戦シーン)では、実際にカメラを投げて撮影をしたそうです。これはもう、ものすごい迫力であり、ナポレオンという人物の非凡さ、特異さ、異常なエネルギー感というものを、映像の力だけで実感できます。
このようにして・・・とにかく80年前の作品なのに、前衛的!創造的!挑戦的!まさに「ナポレオン的」巨大な実験映画になっています。それに比べて、現代はと言えば・・・保守的で、失敗を恐れ、小さくまとまってしまう人が多くなりました。社会全体がそのような風潮に支配されているから、仕方ないのかもしれません。でも、だからこそ、このような閉塞感を打ち破るための「破天荒さ」も、時に必要ではないかと思います。
そして今は、それを他者(自分ではない別の人、ヒーロー)に求めるのではなく、むしろ自分自身の内側に発見することが重要ではないでしょうか。すべての人の心の中には、必ずナポレオンのような勇者は住んでいると思います。その勇者の目を覚まし、共に夢をもって、何かに挑戦する。社会を変える前に、まず自分自身を変えてしまう。と、自分自身に言い聞かせてます。
2010.09.21
18日(土)、「農商工連携人材育成事業」が開校し、私も主催者として、参加いたしました。農商工連携人材育成事業とは、農商工連携に積極的に取り組もうとする人材を発掘し、様々な講義や実施研修を行うことにより、農商工連携に取り組む人的基盤の形成を目的とするものです。すでに農商工連携「認定」を得ている丸二は、日本の森の現状を正しく把握し、積極的に課題を解決しながらビジネスモデルを構想していく人材を広く育成・支援していくために、本事業にもエントリーし、無事「平成22年度・農商工連携等人材育成事業」の採択を受けることができました(林業では全国で2社)。
そして、この日が最初の講座が始まる日だったのですが、おかげさまで定員を上回る約30名の方々からの申込をいただき、大盛況の中で、本事業がスタートいたしました。今回の一連の講座の中で、中心的な講師を勤めていただくのが、NPO法人農商工連携サポートセンター代表理事の大塚洋一郎先生です(写真)。
大塚先生は、経済産業省大臣官房審議官として農商工連携促進法の制定に参画し、その後、農商工連携で地方に雇用を創出することをライフワークとするために、公務員を退職し、農商工連携サポートセンターを設立いたしました。つまり、農商工連携事業の産みの親の一人なのです。
大塚先生の講義をお聞きすると、農商工連携事業の意義、国の方向性、雇用の造り方、自然をいかに守っていくか等の具体的なポイントがよく理解できます。いま、政治がうまく行われていない状況ではありますが、国家として大切なことは、このようにしっかりと地道に進められているということも判ります。
また、これだけ多くの方々が、農業・林業の再生に貢献しようとしているという現実も知ることができ、私たちが取り組んでいる加子母プロジェクトの今後に、またひとつ大きな展望が開けてきました。林業を再生することを通じで、環境を守り、経済力を高め、人々の生活に癒しと健康をお届けすることは、きっと持続可能な仕組みになっていくと思います。
一本の木が育ち、天に向かって上昇していくには、30年、50年、100年という途方もない年月が必要です。多分、この事業もそれくらいの長いスパンで考えていかなければならないでしょう。でも、続けていく限り、数ミリずつ確かに年輪が積み重ねられるはずです。その年輪の数が、地球にとって、人々にとって、私たちにとって、とてつもない資産になっていくと思います。今、私たちは、その苗を植えたところです。
2010.09.13
9月11日(土)~12日(日)、第5回加子母森林ツアーを行いました。この二日間は、研修でもなく、レジャーでもないのに、とても豊かな知識や智慧、気持ちの良さと感動、自然に対する畏敬の念が、ふつふつと静かに湧いてくるような不思議な体験ができる旅となっています。このような経験(思い出)と住まいづくりが一体になると、きっと豊かな日々の生活が待っていると思います。これから住まいづくりやリフォーム等をお考えの方はぜひ、経済産業省(農商工連携事業)認定事業の本ツアーにご参加ください。とても気楽でリラックスできる特別な二日間になることをお約束いたします。
さて、今回のツアーでは、丸二の「加子母ひのきの産地直送・健康エコ住宅」の第1弾「CASIMO1250」のモデルハウスの施工中の様子を観てきました。加子母ひのきの住宅を、関東・東京地域の方々に、手の届く価格帯でご提案しようという思いで、加子母森林組合の皆様と協力して、造りはじめたものです。すでに上棟し、これから内装に入るところです。これから丸二は、1250万円のひのきの家をはじめとして、さまざまなタイプのエコ住宅を、どんどん供給していきますので、御期待ください。
ところで、加子母ひのきの、材料としての特徴は、いろいろとあります。
・強度が一般のひのきよりも15%も強いこと。
・色が独特のピンク色をしていること。
・加子母の裏木曽国有林が伊勢神宮の「式年遷宮」のための御神木に指定されていること。
・自然乾燥にこだわっていること(いつまでも美しい木肌)。
・「緑の循環」森林認証会議による「森林認証」材であること。
つまり、加子母ひのきは、日本中のひのきの中で、歴史的にも、文化的にも、また材料の品質としてもトップクラスのものと言えます。
その加子母ひのきを、丸二は、林業再生のために(直径14㎝未満の場合)一本500円のところを一本1000円で購入させていただき、その分、産地直送という特殊ルートと仕組みによってトータルコストを抑え、コストパフォーマンスの極めて高い商品に仕上げているのです。
さて、下の写真は、二日目に訪れた神宮美林の森です。
ひのきの香りには、様々な効用があります。
・血圧を下げる効果
・瞳孔反射の時間が長くなる効果(=リラックス効果)
・ダニが減少する効果
・森林浴効果(=自律神経を整える効果)
これらはすべて科学的に証明されているものです。それに、ひのきの香りは長く持続しますので、ひのきの住まいに暮らせば、ずっと生涯にわたり長く(この写真のような)森林浴と同じリラックス効果を受けられ続けるのです。これは、とても重要なことだと思います。いま、学校の校舎を木造に戻す方向性が出ていますが、まさにそれは、単なる「自然・エコ」というイメージだけでなく、子どもたちの健康や精神に対する具体的な効用があるからこそと言えます。
山は、いつも見ても変わらずに、そこにあります。でも、実際は少しずつ少しずつ、変化し、成長しています。ひのきの切り株を見ると、木の年輪があり、その木が樹齢何年かが判ります。さほど太くない木でも、自分が生まれるずっと前からそこに在り、一年に年輪一つ分(数ミリ)大きくなっています。そして、少しずつ少しずつ、天に向かって、上へ上へ伸びています。このような仕組み、設計の神秘に惹かれながら、私たちは「ひのき」が喜んでくれるように、森を大切にしながら、最良の建築を目指して行きます。
2010.08.27
私は、サッカーよりも野球世代だったので、サッカーのことをあまり詳しく知りませんが、最近のワールドカップでの日本代表の活躍等を見ていると、それなりに関心を持つようになっています。今朝の日経のスポーツ欄に、三浦知良選手のコラムがあり、何となく読んでみると、なかなか面白かった。
要約すると・・・「今でもサッカーの中心は欧州であり、あえて日本代表の監督として、積極的に欧州から離れる理由はない。異文化では、その土地に合わせた指導が必要で、監督がスペイン人になったからと言って、スペイン代表のサッカーができるわけではない。日本では、ボード上で戦術を語れる人が優れた戦術家だと見られているが、アルゼンチンのメッシ選手のドリブルの前に、多くの戦術は無力だ。ブラジルはピッチ上での表現を大事にする。ボールは人間より速く、人間はボールより速く走れない。」
「人間はボールより速く走れない」・・・この真実の言葉は、とても示唆に富んでいると感じました。何か、そのような一種の道理のようなものを忘れているから、様々な物事に狂いが生じる。その結果、(最近の最悪な例としては)相撲協会の現状があるように思います。
野球と違いサッカーは、個人個人の瞬時のプレーの連続で成り立っていて、野球のように監督やコーチからのサインを見て動くというような管理型スタイルではありません。まさにこれからは、ブラジルサッカーのように、ピッチの上で、個人個人が自らの直観と判断と技術によって(それを信じて)、お互いに息を合わせてゴールを狙う時代なのでしょう。監督やコーチは、そういう場(ステージ)を造ることと、人を造ることが本来の仕事になるのではないかと感じました。
さて、実はそれよりも驚いたのが、このコラムの冒頭に「2014年ワールドカップを目指している僕にとって・・・」という一文あったことです。三浦カズ選手は、まだ夢を諦めていない。どのような経緯があって、今までワールドカップの代表に選ばれなかったのか・・・実際の事はよく知りませんが、この年になっても「可能性がゼロでない限り」夢を諦めないという姿勢と勇気に、心から拍手を送りたいと思います。
そのような意味において、実際にワールドカップに出場できた選手と、出来なくても強く夢や信念を持ち続けている選手と、人間的成長という観点から見て、一体どれほどの差があるのだろうか・・・。三浦知良選手の夢が実現するかどうかは分かりません。でも、何かそこには大切なものがあるように感じました。
2010.08.26
猛暑、熱中症、各地での水の事故等に加え、円高・株安という景気に大きな影響を与える事態も発生し、今年の夏は、本当に「熱い」季節になりました。今後も、様々な分野において、目まぐるしいほどの変化が生まれてくると思いますが、それは時代の大転換期であれば当たり前のことで、客観的に、落ち着いて見守っていかなければいけないと思います。
昔、蒙古が襲来した元寇では、(多少の誇張はあるのかもしれませんが)二度も神風が吹き、日本は守られました。でも、今の日本にはそれだけの運を引き寄せるほどのパワーがあるのか、ないのか。そのような国の本当の実力(財政力とかGDPだけではない、運も含めた総合的な力)が見えてくるのが、これからだと思います。
それは、むしろ国民一人ひとりの意識、心の持ち方、生活習慣、思いやり、暖かさ、エネルギー等の総量によって決まってくるような気がします。景気や経済も、結局人間の活動の結果として、良くなったり悪くなったりするわけですので、人々が明るく元気に動き出せば、きっと良くなるはずです。
今、プロ野球のセ・リーグでは、4位のヤクルトが、知らない間に大躍進をしていて、シーズン途中で監督が代わってから、勝率が65%くらいらしいのです(すごい数字です!)。仮に結果が出なくても、一生懸命、真面目にコツコツ取り組んでいけば、きっと何かのきっかけで、このような奇跡が起こるのでしょう。今後は、様々な場所で、このような思わぬ「良い」展開が、どんどん出てくる可能性があると思います。
昨夜、NHKで「昭和55年」を振り返る番組をやっていました。昭和55年と言うと、私が高校一年の頃でしたが、確かにいろいろとありました。モスクワ・オリンピックへの不参加、大平首相の選挙中の死去、山口百恵の引退、イラン・イラク戦争の勃発・・・「今の時代は大変だから」などと思ってましたが、昔だって、毎年もっと大変な事件や事故や出来事がありました。でも当時は、それらを前向きに乗り越えて行くパワーがあったのではないかと思います。
当時は携帯電話も無いし、パソコンも無い。今の方がずっと恵まれていますし、環境も良くなってますし、あらゆる技術も進歩しています。だから、あとは、私たち一人ひとりの気持ちの持ち様ではないでしょうか。この夏の暑さを、自らの心の「熱さ」に変換して、明るく元気に暖かく!!この素晴らしい夏に感謝です。
2010.08.10

伊勢神宮の御用材、岐阜県加子母の国産ひのき材を使用した住宅「CASIMOシリーズ」の第2弾のイメージ・パースが出来上がりました。まだ細部の修正、変更等がありますが、加子母材と風水設計を組み合わせたシンプルなデザイン性を基調として、エコロジーと住み心地の良さを、リーズナブルな価格(1000万円台後半の予定)でお届けいたします。
構造材は強度の強い加子母のひのき材、内装は床と天井に加子母の天然木材(ひのき、杉等)、壁は健康塗り壁「ダイアトーマス」とし、森林浴の空間イメージと、多様なカラーリング・デザインにも対応しています。
また間取りも、家族のコミュニケーションを大切にしたリビングと各部屋の配置を行い、健康的で、幸福な家庭造りに貢献いたします。お風呂も加子母のひのき風呂を用意、その他、子育て仕様として、ダイニングに子どものための「ひのき基地」を造り、クラフト&スタディー空間に仕上げます。
お父さんのための書斎スペースや収納スぺースにも工夫を凝らし、またリビングには曲線(アール)を取り入れ、脳が癒される、快適な住環境をご提案していきます。照明も間接照明を使い、住まいを優しく美しく、光で満たします。
今後、より詳細が決まり次第、カタログを作成いたしますので、ご興味のある方は、ぜひご連絡をください。また、「加子母森林バスツアー」にもぜひご参加ください。「CASIMOシリーズ」の意義と良さが、より体感できると思います。
地球と家族の未来をより良くするために、丸二は「CASIMIシリーズ」に取り組んでいます。