


2010.08.09
8月に入り、地鎮祭を2件(世田谷と三鷹)行わせていただきました。また、明後日は三鷹にて、さらにお盆明けには3件の予定です。本当に、数多い建設会社の中から丸二をお選びいただいた全てのお客様に対し、心から感謝の意を表します。誠にありがとうございます。
夏の地鎮祭は、猛暑の中での祭事となりますので、いろいろな配慮が必要です。お客様にとっても、そう何度も経験する事ではありませんので、同様に私たちにとっても、一回一回が真剣勝負です。よって、地鎮祭の設営も進行も、決して手を抜かず、毎回立派な祭事になるように心掛け、(夏の場合は)さらに暑さ対策についても、できる限りのことを行っています。
先日の地鎮祭では、お客様より「こんなに立派にしてくれるとは思いませんでした」というお言葉をいただき、本当に嬉しかったです。また、別の日には、祭事を執り行っていただいた神職様より「地鎮祭で、建設会社がお施主様に対して、“誓いの言葉”を述べるのは珍しい。とても素晴らしいことです」と、お褒めの言葉をいただきました。本当に、ありがとうございます。
仮に目立たなくても、できる限りのことをやっていくという姿勢を継続していくことが、一番大切なことだと思っていましたので、これからももっと「より良い」地鎮祭を目指し、改善努力を行っていきたいと思います。土地の神様にご挨拶をして、土地を浄化させていただいてから、土に手を入れるという日本の伝統的な信仰文化は、このようにして(地域の建設会社を通じて)次代へ継承されていくと思います。
また土曜日には、小石川で工事中の「寺院+完全エコロジー型コーポラティブハウス(外断熱+逆梁工法)」である「スクワーバ見樹院(エコビレッジ小石川)」の上棟式が行われました。本プロジェクトの事業主でもある見樹院様による上棟の式が厳かに行われ、駆体(コンクリート構造体)の完成(棟上げ)を皆で祝いました。
このような節目節目における祭事やお祝い事は、やはり日本人の心の原点「感謝」という思いから発生しているように思います。それは、その土地やその取り組みに関わっている人々に対しての感謝に加え、それ以外のすべてのもの(大自然)等への感謝の表現ではないかと。
この上棟式後の食事会の席においても、「丸二さんに決めて良かった」というお言葉を頂戴いたしました。本当にありがとうごいざいます。このお言葉に応えることが私たちの責任であり、仕事です。それは、ただ建物の完成までのことではなく、建物がある限り、一生続いていくものです。そのような職業的責任を果たしていく理念さえ忘れなければ、いかなる時代においても、建設業は信頼される職業として発展して行くと確信しています。
現在、2011年度新卒採用のための会社説明会・面接を行っていますが、その中で、「建設業を通じて、お客様の人生がより良くなるよう、貢献していきたい」というメッセージを送っています。このような考え方を、「一笑に付すことなく」、その可能性を信じ、探求し、実践していく会社にしていきたいからです。
そのような考え方や取り組みは、決して目立たず、評価されにくいものです。それでも丸二は、愚直に、目立たなくても、できる限りのことをやっていくことに、こだわっていこうと思います。
新卒採用説明会の私の発表の最後に、大好きな作家である宮澤賢治の(あの有名な)「雨ニモマケズ」を読みました。人からどのように思われようとも(デクノボーと呼ばれても)、愚直に信じる道を生きて行きたいからです。そういう会社になりたいと思うからです。
[雨ニモマケズ]
雨ニモマケズ
風ニモマケズ
雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ
丈夫ナカラダヲモチ
慾ハナク
決シテ瞋ラズ
イツモシヅカニワラツテイル
一日ニ玄米四合ト
味噌ト少シノ野菜ヲタベ
アラユルコトヲ
ジブンヲカンジョウニ入レズニ
ヨクミキキシワカリ
ソシテワスレズ
野原ノ松ノ林ノ蔭ノ
小サナ萱ブキ小屋ニイテ
東ニ病気ノ子供アレバ
行ツテ看病シテヤリ
西ニ疲レタ母アレバ
行ツテソノ稲ノ束ヲ負ヒ
南ニ死ニソウナ人アレバ
行ツテコハガラナクテモイヽトイヒ
北ニケンクワヤソシヨウガアレバ
ツマラナイカラヤメロトイヒ
ヒデリノトキハナミダヲナガシ
サムサノナツハオロオロアルキ
ミンナニデクノボートヨバレ
ホメラレモセズ
クニモサレズ
サウイウモノニ
ワタシハナリタイ
2010.07.26
今、賃貸経営をお考えのお客様の本音として感じるのは、「本当に入居が決まるだろうか」「それが長続きするだろうか」「実際に掛かる修繕費はこれで済むのだろうか」「施工会社のアフターフォローはしっかりしているだろうか」等の先々への不安が多いということです。その時は良いと思っていても、実際に時間が経過する中で、事業計画が計算通りに行かなくなるのでは・・・という漠然とした不安を感じています。
このような景気の状態ですので、それは当然のことだと思います。これからの賃貸経営には、今まで以上の計画性が必要になってきました。「建てれば入る」という時代ではありません。本当に入居者に喜ばれる住宅、長持ちする住宅、修繕コストが低い住宅、時代にマッチした健康的・環境志向の住宅・・・このような要素を取り入れながら、立地や建築費(融資額)等のバランスを考え、いつまでも地域の他の賃貸マンションよりも優位性のある物件を造ることが重要です。
中でも、特に大切なポイントとして挙げたいのが・・・。先ずは「収納」です。今「おそうじ風水」が流行っていて、住まいの中での整理整頓や掃除が、日々の生活や人生にとって、とても大きなファクターになってきましたが、実際に普通の賃貸住宅に入って整理整頓をするにしても、物を入れる収納があまりにも少なすぎて、とても片づけができる状態にありません。これでは、入居者のストレスも増え、マンション自体の人気も落ちて行くでしょう。かと言って、面積を広くすると家賃も上がり、これも問題です。
二つ目が、「断熱・湿気対策」です。今後はCO2をできるだけ排出しないためにも、断熱効果を上げ、省エネ効果を高めることが重要ですが、同時に室内の湿気を少なくし、カビやダニから住環境を守ることも大切です。湿気によってカビやダニが発生し、室内空気が汚染されると、住んでいる人の健康を損ねますし、同時に壁紙や建材等の老朽化を早めてしまいます。家の中の湿度が高いと、何となく居心地が悪いですし、陰気で不衛生な住環境になりがちです。こうなると、入居者も敬遠していってしまいます。
そしてもう一つは、「修繕費用の低減」です。外観をできるだけ汚れにくい素材にする。内部の湿気を少なくして、クロスや床材等の改修頻度を少なくする。配管スペースを十分に取り、配管の修理・交換コストを大幅軽減する。このような対策を盛り込んだ計画にしておくことで、先々の発生費用を大きく抑えることができ、賃貸経営を安心して進めることができます。
以上の3つのポイントは、当社の「ルネス工法」と「外断熱工法」の二つの工法によって解決が可能ですが、要するに今後は「本当にいい賃貸を建てる」ということを最優先していくことが、賃貸経営を成功させる基本になるのではないかと考えます。入居者の方々に、居心地良く住んでいただく。もう出たくないと思っていただく。なおかつ、計算外の費用も掛からない・・・こういう賃貸経営をあり方を、丸二では日々ご提案しています。
2010.07.22
昨日は「第2回:風水生活セミナー」を開催させていただき、おかげさまで、前回よりも多くのお客様にお集まりいただきました。特に昨日は厳しい猛暑日で、外を歩くだけでも大変だったと思います。本当に心から感謝いたします。
セミナーの内容としては、まず私からは、家の状態を「大極気」「本命気」という2つの気場によって観ることで、家族一人ひとりの部屋割り、ベッドの位置、デスクの位置等の変更方法や、住まいの中にある「殺気」とその回避法についてのお話をしました。特に「本命気」はとても面白く、自分の生まれ年によって、一人ひとりの良い場所、悪い場所が違うので、家族全員の本命気を観ながら、住まい全体をレイアウトしていきます。
ただそれは、あくまで気楽に遊び心で行うもので、同時にあまり家相・方位に縛られないことも重要です。つまり、自分自身にとって、楽しくて、面白くて、いつまでも安心で、居心地が良い住環境をデザインしていくことが本来の目的であり、それが私たちが取り入れている「建築風水」であり、いわゆる一般的な「西に黄色」というような「占い風水」とは違います。
次に、特別講師として、パーソナル風水コンサルタントの種市勝覺(たねいちしょうがく)さんから、より本格的な風水の基本についてのお話をいただきました。種市さんの説明は、とてもわかりやすく(そして、面白く!)、「場(住まい)」の状態が人間の脳と心に、どれだけの影響を与えているのかが、よく理解できます。また、どのような地形、どのような場所に住んだら良いのかも、風水の基本から教えてくれます。ぜひ次回以降も、種市先生の講演をご期待ください。
なお、このセミナーは、風水に関心のある人も無い人も、気楽に参加していただき、紅茶とケーキを味わいながら、平日のお昼前のひとときを寛いでいただくために開催させていただいていますので、ぜひ、ご気軽にお越しください。もしかしたら、セミナーの中で、もっと生活を楽しくするヒントと出会えるかもしれません。
ということで、セミナーの後半は、お茶をしながら、丸二の社員からの「風水あれこれ」的なお話しの始まりです。昨日は、まずリフォーム部の田中慎一君から、色彩と心理についてのレクチャーがあり、どのような色がどのような作用を人間の心理に及ぼすのかを、わかりやすく説明してくれました。そのあと、営業部の鈴木絵理さんから、自身が住まいで実践している事例発表を行いました。これは毎回ユニークな事例で、とても面白いです。
次回は9月15日(水)午前11時からですので、ぜひご気軽に、吉祥寺までお越しください!!
2010.07.20
局地的な豪雨によって、各地で土砂災害が相次いでいます。科学が飛躍的に進歩した現代社会ではありますが、このような自然の力に抵抗するには、未だ人間は無力なのでしょう。かつて、世を治めた偉人たちは、土地の風水を観て、治水や土木の技術を駆使し、都市計画と建築によって町を造り、陣を整え、敵の攻撃から身を守る以前に、自然の猛威をできるだけ受けないような都市環境を造営していました。それが、その当時の政治家にとって最重要課題であり、人民が安心して日々の生活送ることが、世を治めるための基礎にあったからだと思います。
今、BSハイビジョンで「スター・ウォーズ」全6作が放映されています。私は第一作(エピソード4)を、(確か)中学2年生の夏休みに、友達と新宿プラザ劇場に見に行って、大衝撃を受けました。まだコンピューターグラフィックも無い時代に、あれだけの映像を創ることができるなんて、今から考えても凄いことです。それ以降、このシリーズの作品はすべて見ましたが、その中から、「人間は善悪の両方を持っている」「宇宙には、フォースという見えない力が存在している」「人は愛によって救済される」というテーマ性を感じることができました。
自然や宇宙の中には、まだまだ人間が知らない智慧がいっぱいあるように思います。そのすべてを理解することは到底不可能なのですから、先ずは、それらすべてに対しての感謝と謙虚の心を持って、畏敬の念を持ち続けたいと思います。そういう意識を持つことによって、もっと自然と共生するためのアイデアが生まれて来るような気がします。
さて私たちは、そのような自然の力を、「木」を通じて学ぼうとしています。加子母ひのきの伐採現場では、ひのきの香りの不思議、年輪の不思議を感じます。木という存在自体も、考えれば考えるほど不思議です。自然との共生は、最終的には人間の側に学ぶ姿勢がなければ、不可能ではないかと気づきました。自然と人間は対等ではないと。ここが、災害対策のために必要な認識ではないかと思います。
※ウィーンフィルの「スター・ウォーズ」!
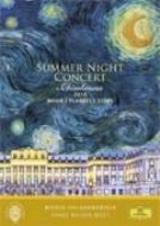
『シェーンブルン宮殿 夏の夜のコンサート2010』 ヴェルザー=メスト&ウィーン・フィル
天下のウィーンフィルが、映画音楽の「スター・ウォーズ」を演奏したということで、(ごく一部で)話題になっているDVDです。シェーブルン宮殿の野外コンサートということなので、イベント的な要素も強いですが、なかなか面白いです。他のプログラムに、ホルストの「惑星」から「火星」も入ってます。「惑星」も、随分昔に冨田勲のシンセサイザー版を聞いてから、好きになりました。宇宙、SF、自然科学という分野には、常に興味があります。
2010.07.12
10日(土)~11日(日)、第4回岐阜県・加子母森林ツアーを開催いたしました。心配された天気も、初日は晴天、二日目も雨が降る前にすべての見学を終え、とてもラッキーな二日間となりました。今回は20名のツアーで、加子母森林組合さんの取り組みや山や林業の現状を学びながら、パワースポットとも言える加子母の神宮美林を歩き、都会の喧騒から離れた場所で、自然との触れ合いを体感できたと思います。
歴史的に、加子母の山のひのきは、とても神聖なものであり、今でも伊勢神宮の御用材として有名です。しかしながら、そのような由緒ある森を護ることは、実際にはとても厳しく大変なことです。それでも、永きにわたり、この加子母の山が護られ続けているのは、加子母の人々たちの「森を護る。森・自然へ感謝する」という強い思いが、代々受け継がれているからではないかと、感じるのです。すべてが森を護ることと結びついている。それ以上のものは不要である。加子母にいると、そのような「気」を感じます。
それでも、私たちのような「よそ者」が来ても、懐深く受け入れていただき、歓迎してくださる。雨雲をちょっと避けてくださる。そのような「加子母宇宙」に対して、私たちは、一体どのような貢献が出来るのだろうと、ふと考えます。私たちは、適切な間伐をすることが、森を護ることだと知りました。しかしながら、だからと言って、むやみやたらに(当たり前のように)木を伐るのではなく、「人々の暮らしのために、使わせていただきます。ごめんなさい。ありがとうございます」と言う、強い強い畏敬の念と感謝の気持ちを忘れないことが大切だと考えています。
私たちは、今後も森林ツアーを続けてまいりますので、ぜひご参加ください。この二日間で、とても大切な何かを学ぶことができると思います。また、「家」とは「人生を造る場(宇宙)」のことを言います。人生を造る場に、どのような材料が使われているのかを、家主は知る権利(責任)があると思います。加子母の山に行って、ぜひ、その答えを見つけていただきたいと思います。
さて、参議院議員選挙が終わり、盛り上がったワールドカップも終わりました。短い期間で振り子が大きく振れたり、予測もしにくい時代になりましたが、これは大変化の兆しです。前向きに、楽しみながら、ジェットコースターに乗ることでしょう。いよいよ新しい時代が始まりそうで、ワクワクします。
2010.07.01
ワールドカップが終わりました。決してサッカーの国ではない日本が、あそこまで戦えるようになったのを見て、世界はきっと驚いたと思います。素人目から見ても、本当に日本代表は強くなりました。今までのような大物スター選手がいなくても、チームワークで勝つことができることを、岡田監督は証明したかったのかなと思います。もしそうであるならば、十分その目的は果たせたのではないでしょうか。
また、この大会で初めて本田選手のことを知りましたが、本当に真面目な勉強家なんですね。ずっと「サッカー日記」を付けていて、夢を持って、懸命に精進していたのだと思います。きっと家族、兄弟、親戚やまわりの環境のおかげもあったのでしょう。こういう人が、今後日本の政治の世界にも現れて、活躍してくれることを期待しています。
逆に参議院選挙の方は、あまり盛り上がっていないようです。今回は、消費税についての考え方が焦点の一つになってきましたが、二大政党の両方ともが増税を掲げなくてはならないほど、国の財政が厳しいことはよく分かりました。その上で、どのようにしてこの難局を乗り越えていくのか。もう少し根本的な部分に踏み込んで、長期的に日本を強くするためのビジョンを示し、サッカー日本代表のように、捨て身になって、時代や状況と戦って欲しいと思います。国民もみんな、日々戦っていますから。
変化、進化が、今こそ求められています、変化、進化が止まると、会社も国家も終わりです。勇気を持って、あえて変化をつくる。そのような精神と積極的な姿勢が、現状をブレイクスルーする唯一の道だと思います。
※サロネンのマーラー
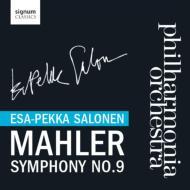
マーラー/交響曲第9番 サロネン&フィルハーモニア管弦楽団
先日紹介したサロネンのマーラー9番が出たので、早速聴いてみました。明らかに今までの他の演奏とは違い、とても独創的です。マーラーと言うと、もっと重くて暗いイメージがあるのですが、この演奏はとてもダイナミックで音楽的でスリリング。それなのに、アダージョは美しくて神秘的・・・マーラーの深くて精神的な部分が伝わります。不思議なオリジナリティ・・・これが、丸二が求めているものか。
2010.06.24
昨日、岐阜県加子母にて、加子母ヒノキの健康エコ住宅「CASIMO1250/1550」の商品発表を行いました。


伊勢神宮の御用材として有名な加子母ヒノキで造られた家を、できるだけ安価で都会の方々へお届けしたい。と同時に、直径14㎝未満の特別有効利用材の価格を現在一本500円のところ、倍の1000円で購入させていただき、森の経済にも貢献したい。それらが結果的に、都会に住む人々の健康と日本の森を守ることにきっとつながる。
そのようなコンセプトを持って、一棟1250万円の加子母ヒノキ住宅を開発いたしました。1250万円という価格は、加子母森林組合が、極めて優良な森林認証材を「産地直送システム」で丸二に送っていただけることで実現可能となりました。
また、本事業が、国の経済産業省と農林水産省が推進する「農商工連携事業」の認定を受けたこともあり、様々な方々からのご支援、応援もいただいています。本当に感謝、感謝です。
丸二は、日本の森や山の恵みに感謝をして、「使わせていただく」という気持ちを忘れずに、今後の木造事業に積極的に取り組んでまいります。尚、この「CASIMO1250/1550」開発への思いを下記にまとめましたので、ぜひお読みください。詳細資料につきましては、お問い合わせをいただいた方にお届けいたします。
「CASIMO1250/1550」開発の動機
1.日本の森を守りたい。
間伐によって、森に光を入れることが、日本の森を守る道であることを知り、国産無垢材をふんだんに使った木造住宅事業を始める決心をいたしました。今、日本の森は荒れ、自然災害も増え、生態系や景観も壊れつつあります。日本で使われている木材の80%が外国産であり、国産材の需要が極めて低いことも大きな要因のひとつです。私たちは、この美しい日本の山々からの恵みを授かって、豊かな生活をさせていただいています。しかしながら、そのような自然の恩恵に対する感謝の気持ちは、今や失われつつあります。だからこそ丸二は、少しずつ、自然界への恩返しを始めようと思うのです。適切な量の木を、(山の立場から見て)適正な価格(直径14㎝未満の特別有効利用材一本500円を1000円で購入いたします)で使わせていただき、山に対する経済的貢献を果たしつつ、森に光を入れ、新しい木を植え、育て、森を守ることに参画していきます。その結果、加子母森林組合の皆様を始めとする、21世紀の中心産業となる林業(第一次産業)の発展と地球環境の保護に貢献してまいります。
2.誰もが国産ヒノキの家に住めるようにしたい。
先行きが見えない厳しい経済環境の中で、誰もが安心して暮らすことのできる住環境を提供していくことが、これからの私たちの社会的使命です。加子母森林組合様の大変なご厚意による(業界の常識を飛び越えた)「産地直送システム」の導入と、設計施工に関わるコストへの挑戦によって、「ヒノキだから高い」「良いものは高くて当たり前」という固定観念を打ち破り、多くの人々の手に届く価格帯で、本物の自然住宅を提供していきたいと思います。加子母地域の神宮美林で育った木々は、日本の建築・精神文化の歴史的象徴であり、住宅用材としての特性の良さはもちろんのこと、すべての日本人にとって、大いなる精神的な拠り所(大黒柱)となるはずです。色も香りも素晴らしい加子母ヒノキで造られた家に住むということは、自然の素材による安心感以上に、「護られている」という無形の価値を得ることでもあります。私たちは、加子母の木々を使わせていただき、健康的で、癒し効果の高い住宅を広く社会にお届けしていきます。また、そこには「風水」「建築医学」の智慧も取り入れ、デザイン性も大切にし、住む人の楽しさや喜び、そして心と体の健康を実現してまいります。孫の代まで3世代(100年間)、地球と家族の未来を育み続ける家であるように・・・それが、私たちの目指している「最善の住環境」です。
3.創業の精神に回帰したい。
私の祖父、渡辺二郎は、岩手県松尾村での製材所経営を経て、東京都武蔵野市吉祥寺にて丸二を創業した父、渡辺正一(現会長)と共に、木造住宅の建設事業を始めました。それから約60年・・・高度成長の時代の流れに乗って、丸二の建築の主体は、鉄筋コンクリート造へと変わり、木造住宅の施工実績はどんどん減少していきました。しかしながら「最善の住環境」を標榜する私たちが、その最善さを追求するにつれて、どうしても「木」と向き合う必要が出てきました。本物の住環境を実現するには「無垢材」「木造」しかないと。しかしながら木造事業を立ち上げるのは、今となっては新規事業。ちょうどその時、今回の農商工連携事業、そして加子母森林組合の内木組合長様との出会いがあり、とうとう思いの実現に向けてキックオフするに至りました。確かに、木造事業としては新規スタートではありますが、木造に対する理念は、今でもしっかり継承されています。今では、当時の祖父や父たちの「木に対する強い思い」こそが、今回の出会いを導いたのではないかと感じています。このようにして、今こそ創業の精神に回帰し、21世紀の丸二の新たなる道を、社員と共に歩んでいく決意です。それが、「最善の住環境」を実現する王道であり、また同時に、社員に対する技術教育、人格形成に結び付くものであると信じています。
以上のような思いを持って、丸二は「CASIMO」で、社会に貢献していきます。
2010.06.09
少しブログを書かないうちに、政治が大きく動き、(地元武蔵野市選出の)菅さんが首相となり、菅新内閣が誕生しました。一方、鳩山さんは政権交代という目標を達成しましたが、短期政権に終わってしまいました。一寸先は闇の政治の世界ですが、本当に先は分からないものです。
日本はとても良い国です。不況とは言いながら、他国の困窮状態に比べれば、全体的には豊かな生活ができています。国の財政状態も確かに年々悪化してはいますが、外国から借りているわけではなく、これも他国の状況とは随分違います。
もちろん、かつての日本の力からすると、加速度的に落ちていることは事実です。きっと一時的に豊かになり、緊張感を失い、無駄遣いを始めてしまったからでしょう。それに、国としてのその後の長期的な戦略(夢)を立てることができず、効果的な将来への投資ができなかったことも原因の一つかもしれません。
ただ、これらすべてを政治家のせいにするわけにもいきません。長い間、「自分が得するかどうか」で投票をしてきた国民の側にも、いくらかの責任があると思います。国民の意識の投影が、表舞台に現れているわけですから・・・恥ずかしいです。
でも、このような困った状況になることで、私たちはいよいよ考え始めます。日本の将来を真剣に考えるようになります。そういう意味も含めて、とても良い状態になりました。今後の日本に大いに期待しましょう。
尚、先日「第3回:加子母森林ツアー」を開催し、30名の方々と共に、一泊二日で加子母の山に行きました。日本の山は、自然、資源、動植物、スピリチュアリティの宝庫です。この美しい日本の風景を守っていくことも、私たちの大きな夢のひとつです。
※「第3回:加子母森林ツアー」の模様を、今年の新入社員がブログにアップしていますので、ぜひご覧ください(1日目と2日目)。また御関心のある方は、今後の開催予定をご覧ください。
※サロネン指揮の「幻想交響曲」
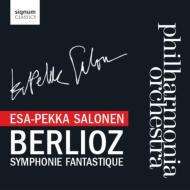
ベルリオーズ:幻想交響曲 サロネン&フィルハーモニア管弦楽団
最近、素晴らしい演奏を聴きました。指揮はフィンランド出身の気鋭エサ=ペッカ・サロネンで、オーケストラは英国のフィルハーモニア管弦楽団。サロネンは、まだあまり有名ではないですが、私が今最も好きな現役指揮者です。何がいいのかというと、美しい北欧デザインの家具のようです。ちょっとうまく表現できないのですが・・・。曲はフランスの作曲家ベルリオーズの「幻想交響曲」で、「若い芸術家が失恋をして、阿片自殺を図るが死に至らず、奇怪で幻想的な夢を見る」という内容の、それまでに全く無かった種類の音楽です。その奇怪さや幻想感が、サロネンの美しくパワフルな指揮によって、色彩豊かに響き渡り、はじめてこの曲を聴いて感動することができました。今度はマーラーの第9番が出るそうなので、必ず聴こうと思います。
2010.05.26
先日(5月19日)丸二本社にて、「第1回風水生活セミナー」を開催させていただきました。ご参加いただいた皆様に、心から感謝いたします。本セミナーは、通常とは少し雰囲気を変えて、平日の午前11時からお昼の12時30分までの時間帯とし、ケーキと紅茶を楽しみながら、気楽に住まいの環境についての情報提供をするもので、とにかく敷居の低さと参加のしやすさを一番のコンセプトにしたものです。
「風水生活」とは、多くの人々が日常生活の中で無意識のうちに影響を受けている「環境ストレス」を緩和させることで、心と体を健やかに改善することを目的とした生活の在り方を言います。「風水」というと、どうしても占い的、方位学的なイメージが付いて回りますが、私たちは、あくまで建築(住まい)と自然環境との調和を優先させ、かつ統計学的な要素と大脳生理学的な要素も加え、多くの方々に理解しやすい実践的なご提案をしています。今後も、二か月ごとに開催する予定ですので、ぜひご気軽にご参加ください。
尚、美しい音楽をきれいな音で聞くことも、ひとつの風水生活ですね。仕事から帰った後、リビングで寛ぎながら好きな音楽を聞くと、心が癒され、気持ちも前向きになり、明日への活力も湧いてきます。例えば、マーラーの交響曲第2番「復活」の最終楽章を聞くと、大きな感動と共に、明日へのやる気で満たされるはずです。そのようにして、日常の生活の中に、「感動」や「癒し」をインストールし、自分自身の感情をより良い方向へ導いていくことが風水生活のひとつですし、それは住まい造りと密接な関係性があるのです。
※迫力満点のマーラー:交響曲第2番「復活」
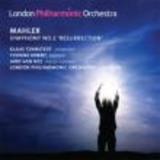
交響曲第2番『復活』 テンシュテット&ロンドン・フィル(1989 ステレオ)
少し前に発売された、マーラー指揮者の第一人者テンシュテットの1989年ライヴ盤です。音質はまあまあですが、音楽はとても素晴らしく感動的です。かなり長い曲なので、終楽章だけでもいいですね。マーラーは、本当にすべての交響曲が感動的です。
2010.05.25
先日、第18回安全衛生大会を開催し、約80社の協力会社の皆様にお集まりいただきました。一年に一度、安全に対する意識を高め、無事故・無災害の現場管理を継続していくために、非常に重要な機会です。
今回も、一昨年に引き続き、建設業労働災害防止協会の中込平一郎先生に記念講演をお願いし、「物から人へそして組織へ・・・安全のうつり変わり」というテーマでのお話をいただきました。その中で、日本は「恥」の文化であり、「ルールを守らない」などと言う「みっともないこと」はしない国民性があった・・・とお聞きしました。
そう考えた時に、今の日本は大丈夫だろうかと考えます。ルールを守る、規律を守る、約束を守る・・・という基本を軽んじてはいないかと。それは、現場の安全のみならず、人生の安全に関わることと、あらためて認識しました。
また、私の挨拶としては、現在の業界に対する考え方を話させていただきました。つまり、「建設業界」は、とても良い方向に向かっていると。今までのような利益第一の業界体質から、本当にお客様本位の世界に変わってきました。
つまり今までは、「まず利益、次に技術、最後に心」でした。でもこれからは、「まず心、次に技術、利益は後から(きちんと)付いてくる」、このように180度の大転換が始まったと感じています。とすれば、今までひたむきに、考え方や心がけを大事にして、良い仕事を目指してきた会社(人、職人さん)にとっては、やっと光が当たる時代になったということです。
丸二も、十数年前から、そのような時代に備えて、出来る限りの準備をしてきました。何度、逆戻りしそうになったか分かりません。でも、その「決心」をもって、心を第一とする感謝経営を持続してきました。もちろん、まだまだその道は半ばですが、新時代のゲートが開き始めた今、大いなる自信を持って、お客様や社会に貢献していきたいと思います。丸二にとっての安全とは、挑戦の文化です。